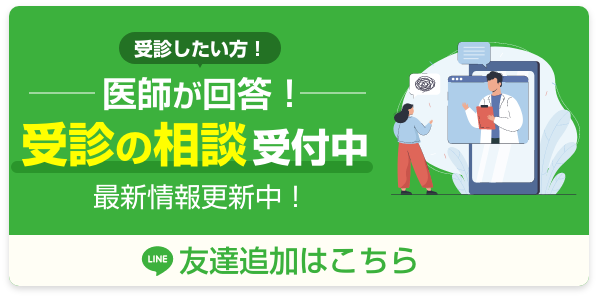年代別に膝の痛みの症状をチェック|考えられる疾患や受診の目安は?

膝の痛みは、年齢によって原因や症状の出方が異なります。
正しい対処をするためには、自分の年代に合った特徴や疾患を知ることが大切です。
本記事では膝が痛むときのチェックポイントから考えられる原因、受診の目安まで分かりやすく解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
膝が痛いと感じたとき最初にチェックしたいポイント
まずは自身の膝の状態を把握し、痛みの原因を正しく探ることが大切です。
膝のどこが痛いか
内側・外側・前面・裏面など、痛みの部位によって原因となる疾患が異なります。
動かしたときに痛みが生じる場合は、少し指で押したり、ゆっくりと曲げ伸ばしをしたりしながら確認しましょう。
痛みが出るタイミング
歩き始めや階段の昇り降り・長時間座った後など、痛みが現れるタイミングも重要な判断材料となります。
違和感・腫れ・不安定さ
見た目には何の変わりもない場合もあれば、腫れや熱感・ぐらつきが見られる場合もあります。
症状が日を追うごとに変化するときは、こうした症状をメモにとっておき、診察の際に医師へ伝えると安心です。
関連記事:膝の痛みで病院に行くタイミングとは?治療と再発予防のポイントを解説
10〜30代に多い膝の痛みをチェック
若年層では、スポーツや怪我による膝の痛みが多く見られます。
次の症状のうち、当てはまるものがないかチェックしましょう。
症状チェック
- スポーツや転倒などで膝をひねった経験がある
- ジャンプや急停止のあと、膝がズレた・抜けたように感じた
- 膝の中でカクッと引っかかるような違和感がある
- 屈伸動作で膝に痛みや不快感がある
- 運動後に膝が腫れたり熱を持つことがある
- 膝のお皿が外れるような不安定感がある
- 膝の下(脛の上部)が出っ張っていて押すと痛い
考えられる主な疾患
- 半月板損傷
- 有痛性分裂膝蓋骨
- 離断性骨軟骨炎
- 関節リウマチ
- 前十字靭帯損傷
- 膝蓋骨亜脱臼
- オスグッド病
- 関節内の炎症
- 捻挫
- 疲労骨折
受診や対処のポイント
- スポーツによる怪我に強い整形外科の受診を検討
- MRIなどの精密検査を積極的に受ける
- まずは安静を心掛け、アイシングやサポーターを使用
- 理学療法士のアドバイスを受けながらリハビリで筋力バランスを整える
関連記事:膝の痛みは自分で治せる?膝が痛む原因とセルフケア方法を解説
40〜50代に多い膝の痛みをチェック
中年以降は、軟骨のすり減りや姿勢の癖による慢性的な痛みが増えてきます。
症状チェック
- 階段を下りるときに膝が痛む
- 動き始めに膝がこわばる・違和感があるが、動かすと和らぐ
- 膝を曲げるときに突っ張るような感覚がある
- 膝の内側や前側がじわじわ痛む
- 膝の曲げ伸ばしでポキポキ音がする
- 座ってから立ち上がるときに痛みや不安定感がある
- 体重増加や加齢により膝に痛みを感じるようになった
考えられる主な疾患
- 変形性膝関節症
- 関節リウマチ
- 半月板損傷
- 滑膜ひだ症候群
- 鵞足炎
- 痛風
- 筋肉由来の痛み
受診や対処のポイント
- 整形外科でレントゲンやMRIを受け正しい原因を特定する
- ストレッチや筋トレで膝周りの筋肉を強化する
- 早めの治療によって進行を防ぐことが重要
60代以降に多い膝の痛みをチェック
高齢層では関節の変形や軟骨の摩耗が進行し、日常生活に支障をきたすことがあります。
症状チェック
- 膝の内側や外側に慢性的な痛みがある
- 歩くだけで膝がズキズキ痛む
- 膝が腫れていたり、水がたまっていると感じる
- 正座やしゃがむのが難しくなってきた
- 夜間や安静時にも膝が痛むことがある
- 膝の変形(O脚・X脚)が気になっている
- 体重をかけると膝がグラつく、不安定に感じる
考えられる主な疾患
- 変形性膝関節症
- 関節リウマチ
- 大腿骨内顆骨壊死
- 骨粗鬆症による骨折
- 半月板損傷
- 鵞足炎
- 筋肉由来の痛み
受診や治療のポイント
- 理学療法士の施術
- 薬物療法(内服、外用、ヒアルロン酸注射)
- ハイドロリリース
- 体外衝撃波治療(拡散型、集束型)
- 再生医療(幹細胞治療、成長因子療法、幹細胞上清液療法)
- 手術療法(関節鏡手術、人工関節置換術、骨切り術)
膝の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで
膝の痛みにお悩みの方は、イノルト整形外科の受診をご検討ください。
当院は関節外来にて、患者様の状態に合わせた検査・治療が可能です。
レントゲンや超音波・MRIを用いた正確な診断を経た後、再生医療や体外衝撃波、ハイドロリリース、理学療法士の施術など幅広い保存療法から合うものを選択し、手術を受けずとも痛みの改善を目指します。
さらに、必要に応じて専門手術が得意な医療機関と連携しながら、患者様が快適に日常を過ごすためのサポートを行います。まずはお近くの整形外科へご相談ください。
関連記事:膝が痛い時の対処法は?やってはいけないことや受診のポイントを解説
まとめ
膝の痛みは年代ごとに原因が異なり、いずれも早期の対処が将来的な悪化を防ぐポイントとなります。
気になる症状がある方は、年齢や生活背景に合った対処を心掛けるとともに、必要に応じて整形外科を受診しましょう。
膝の痛みに悩んでいる方や、医療機関への受診に不安がある方は、イノルト整形外科へお気軽にお越しください。
首の痛みでよくみられる症状は?考えられる原因や注意すべきケースを解説

首の痛みは、ストレートネックや頚椎症・ヘルニア・むちうちなどさまざまな原因が考えられます。
日常の習慣が影響している場合も多く、進行すると日常生活が不便になることも。
本記事では首の痛みに良く見られる症状や原因・注意すべきケースなどを詳しく解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
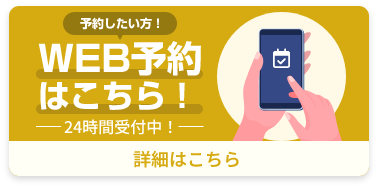
首の痛みでよくみられる症状

一言で首の痛みといっても、その症状はさまざまです。
朝起きたときに首が動かない
寝違えたときの代表的な症状であり、首の筋肉が一時的に炎症を起こしている状態です。
寝返りがうまくできなかったり、枕の位置が合わなかったりといった原因で起こります。
デスクワーク後に首が重だるい
長時間のパソコン作業やスマホ操作により、首の後ろから肩にかけての筋肉が緊張することがあります。
これにより「締め付けられているような痛み」や「だるさ」が現れるほか、目の疲れや頭痛を併発することもあります。
後ろを振り向くと痛みが出る
首の可動域が狭くなり、動かす際に関節や筋肉がひっかかるように感じる場合もあります。
これらは頸椎周辺の関節に問題がある場合が多く、症状が悪化すると痛みにつながります。
関連記事:首筋が痛いときはどうする?自分でできる対策と整形外科での治療方法を解説
首の痛みの原因として考えられる疾患
首の痛みには、さまざまな疾患が隠れている場合があります。
医療機関を受診しなければならないものもあるため、自分の症状と照らし合わせて確認しましょう。
首こり、肩こり
多くの日本人が経験する症状であり、筋肉の緊張によって起こります。
長時間のデスクワークやストレスによって起こりやすい疾患です。
ストレートネック
頸椎は普段自然なカーブを描いていますが、このカーブが失われてまっすぐになると、首への負担が増えて痛みや違和感を引き起こします。
スマホやパソコンの使用時に前かがみになることが原因です。
頚椎症
加齢によって頸椎の椎間板がすり減り、「骨棘(こつきょく)」ができて神経を圧迫します。
首や肩の痛み・しびれ・可動域の制限が見られます。
頚椎椎間板ヘルニア
頚椎椎間板ヘルニアは、椎間板が突出して神経を圧迫することで、首の痛みや腕のしびれ・筋力低下などの症状が現れます。
放置すると症状が悪化する可能性があるため、早期の診断と治療が必要です。
むちうち
交通事故やスポーツなど首に急激な衝撃が加わることで、筋肉や靭帯が損傷する外傷性の疾患です。
首の痛みのほか、可動域の制限や頭痛・めまいが起こる場合もあります。
首の痛みを引き起こす日常生活の習慣

首の痛みは日常的な習慣によっても起こりやすいため、下記に当てはまる場合は注意が必要です。
長時間のスマホ・パソコン作業
スマホやパソコンを長時間使用することにより、首が前傾し、筋肉に負担がかかります。
定期的な休憩や姿勢の見直しが重要です。
不良姿勢や猫背
猫背など前かがみの姿勢は、首や肩の筋肉に負担をかけ、痛みやこりの原因となります。
正しい姿勢を意識し、背筋が伸びた状態を保ちましょう。
枕が合っていない
枕の高さや硬さが合っていないと、首に不自然な力が加わり、痛みの原因となります。
自分の高さに合う枕を選ぶことはもちろん、寝返りのしやすさなどを実際に使って確かめてみることが大切です。
ストレスや緊張による筋肉のこわばり
ストレスや不安によって筋肉が硬直すると、首や肩の痛みを誘発します。
ストレスフルな環境では、積極的にリラクゼーションやストレス発散法を取り入れましょう。
関連記事:関節痛の治し方|主な原因や自宅でできる対処方法とは?
首の痛みをやわらげるセルフケア
首の痛みが軽度な場合や、セルフケアによって回復の手助けをしてあげることも有効です。
短時間の休憩と姿勢の見直し
長時間同じ姿勢を続けることは避け、1時間に1回は立ち上がって軽いストレッチを行いましょう。
正しい姿勢を心掛け、筋肉や靭帯が不自然な形で固まらないように注意が必要です。
湯船に浸かって首を温める
入浴時はできるだけ湯船にお湯をはり、首や肩を温めます。
血行が促進され、筋肉の緊張が緩和しやすくなります。
ストレッチで筋肉をほぐす
首や肩のストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性が向上し、痛みやこりの予防・改善につながります。
枕を見直してみる
枕の高さや硬さを調整し、自分に合った枕を使用することが大切です。
店頭で実際の枕に触れてみたり、専門店でアドバイスを受けたりすることもおすすめです。
首の痛みで注意すべきケース

下記のようなケースは、セルフケアでの改善が期待できず、放置するとさらに症状が悪化する危険性があります。
早い段階で整形外科などの専門医へ相談しましょう。
しびれや感覚異常がある
首の痛みに加え、腕や手のしびれ・感覚異常がある場合は、神経の圧迫が疑われます。
痛みが広がる・悪化する
痛みや首から肩・腕へと広がったり、日々悪化したりする場合は、胸郭出口症候群や頚椎症性神経根症、椎間板ヘルニアなどの疾患が進行している可能性があります。
長引いて日常生活に支障が出ている
首の痛みが数週間異常続き、日常生活に支障をきたす場合、専門医の診察にて原因や適切な治療を判断してもらう必要があります。
関連記事:ロキソプロフェンが効かない?痛み止めで腰痛や首の痛みが取れない原因
首の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで

イノルト整形外科では、首の痛みに関する専門的な治療を行っています。
脊椎外来では、最新の医療機器を用いた診断と、患者様一人ひとりに合わせた治療プランを提供可能です。
首の痛みはもちろん、腰痛や側弯症・椎間板ヘルニアなどさまざまな疾患に対応でき、原因に即した治療を行います。
どんな疾患においても、まずは専門医の診察を受け、正しい原因を探ることが大切です。
首の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
首の痛みは、日常生活の習慣や姿勢・ストレスなどさまざまな要因によって引き起こされます。
セルフケアで対処ができない場合も多いため、適切な治療法を探るためにも、早めの段階でイノルト整形外科までご相談ください。
半月板損傷の症状チェック|初期症状や変形性膝関節症との違いは?
今回ご紹介した症状や受診目安を参考に、該当する項目があった場合には早めに整形外科を受診し適切な治療を受けましょう。

スポーツの際に膝を強く打ったり、ひねる動作が加わった後に痛みが現れた場合、半月板損傷の可能性が考えられます。
しかし、痛みの程度もさまざまで、病院を受診すべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、半月板損傷の典型的な症状や、病院を受診すべき目安やチェック項目について詳しく解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
半月板損傷の症状チェック

半月板損傷を発症した場合、どういった症状が現れるのでしょうか。簡易的にチェックするために代表的な症状をご紹介します。
以下の症状に該当した場合には早めに整形外科を受診しましょう。
膝に引っかかりを感じる
膝の曲げ伸ばしの際にスムーズに動かず、途中で引っかかるような違和感がある場合、半月板損傷が疑われます。
症状としては軽度で初期段階にあたるため、早めに治療をすることで早期に回復できる可能性があります。
膝が安定しない
膝がぐらついたり、踏ん張れない、あるいは体重をかけた際に不安定感を覚える場合は、半月板の損傷によって膝関節のバランスが崩れている可能性があります。
特に、歩行時や階段の上り下りの際に膝に力が入らず、崩れ落ちるような感覚は半月板損傷で現れることのある症状です。
歩行時の膝の痛み
歩行時に膝の内側や外側に鋭い痛みを感じる場合、半月板が損傷している可能性があります。
特に、歩行後や運動後に痛みが増す場合は半月板損傷が疑われますが、ほかの疾患も考えられるため整形外科でのレントゲンやMRI検査が必要です。
膝の曲げ伸ばしができない
膝に引っ掛かりや違和感があるものの、治療をせず放置しておくと、やがてロッキングとよばれる状態に陥ることがあります。
ロッキングとは膝の曲げ伸ばしができなくなる状態のことで、安静時にも強い痛みを感じるケースが少なくありません。
膝が腫れている
半月板が損傷すると、関節内に炎症が起こり膝が腫れることがあります。
膝関節には関節の動きをスムーズにする関節液が溜まっていますが、炎症が起こると関節液が過剰に分泌されます。
これは、いわゆる”膝に水が溜まった状態”で、膝が大きく腫れ曲げ伸ばしがしづらくなることがあります。
膝を負傷するとたびたび水が溜まりやすくなるため、頻繁に腫れる場合には放置せずに医師の診察を受けましょう。
関連記事:半月板損傷の軽度な場合について治療について解説|手術しないで治すことは可能か?
半月板損傷とは?

半月板損傷とは、膝関節にある半月板という組織が損傷し、痛みや炎症を伴う疾患です。
そもそも、半月板はどういった役割を果たしているのか、半月板が損傷する主な原因についても解説しましょう。
半月板の役割
半月板は、膝関節の内側と外側に1つずつ存在するC字型の軟骨組織です。
歩行やジャンプ動作などの際に、膝関節にかかる衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしています。
また、半月板が存在することで膝にかかる体重が適度に分散され、膝関節の安定性を保ちスムーズな曲げ伸ばしもサポートできるのです。
半月板損傷の原因
半月板損傷は、大きく分けて外傷性と変性(加齢)の2つのタイプに分類されます。
1.外傷性
外傷性の半月板損傷は、スポーツや事故による膝への強い衝撃や、急激なねじれ動作などが原因で発症します。
典型的な例は以下の通りです。
- ジャンプの着地や、ダッシュからの急停止など(バスケットボール・バレーボール など)
- 急な方向転換や足の回転動作(サッカー・テニス・スキー など)
- タックルや転倒による強い衝撃(ラグビー・柔道・相撲 など)
外傷性の半月板損傷は、前十字靭帯(ACL)損傷と同時に発生するケースも多く、損傷度合いによっては手術が必要になることもあります。
2.変性
変性の半月板損傷は、加齢に伴い半月板の弾力性が低下し、しゃがむ・立ち上がるといった日常生活の動作が原因で発症します。
主に40代以上に発症しやすく、外傷がないにもかかわらず膝に違和感や痛みを感じるようになります。
初期段階では、膝を曲げたり伸ばしたりした際に引っかかる感覚が特徴的です。
また、若年層であっても急激な体重増加によって膝に大きな負担がかかり、半月板の形が徐々に変性していくこともあります。
変性の半月板損傷は変形性膝関節症の前兆となることも多いため、早めの治療が重要です。
半月板損傷の初期症状と経過

半月板損傷はどのように進行していくのか、初期から進行期にかけての主な症状を解説しましょう。
初期の主な症状
初期段階に現れる代表的な症状は以下の通りです。
- 膝の痛み
- 膝の引っかかり感
- 膝の腫れ・圧迫感
初期段階の痛みは一時的なもので、1週間程度が経過すると徐々に治まっていくことも多いです。
しかし、その後膝関節の引っ掛かり感や違和感を覚えるようになり、徐々に腫れてくるケースも少なくありません。
安静時には痛みが落ち着くことが多いため、治療を放置し状態が悪化する患者様も少なくありません。
中期の主な症状
治療が遅れると徐々に症状が進行していき、以下のような状態になります。
- 痛みが強くなり、歩行や運動に支障をきたす
- 階段の下りや坂道で痛みが悪化
- 膝のロッキングが起こり曲げ伸ばしができなくなる
- 膝に水が溜まり、しゃがむ姿勢や正座が困難になる
- 膝のぐらつきや不安定感が強くなる
初期段階から進行していくと、徐々に痛みが強くなります。
特に下り坂や階段を下りる際に強い痛みを感じ、関節も不安定になり力が入らなくなります。
進行期の主な症状
痛みが強まっているにもかかわらず治療をせず放置しておくと、重症化し以下のような症状が現れます。
- 慢性的な膝の痛みで日常生活が困難になる
- 膝の可動域が極端に狭くなり、こわばりが生じる
- 軟骨が摩耗し変形性膝関節症を発症する
- 人工関節置換術などの手術が必要になるケースもある
進行期では強い痛みによって日常生活にもさまざまな支障をきたします。
関節のバランスが崩れることで軟骨が摩耗し、変形性膝関節症につながるケースも少なくありません。
関連記事:半月板損傷でやってはいけないこととは?早く治す方法も解説!
半月板損傷と変形性膝関節症の違い

半月板損傷と並び、膝の痛みの原因になる疾患として多いのが変形性膝関節症です。
両者はどういった違いがあるのか、原因や痛みの出方、治療方法などを解説しましょう。
原因
半月板損傷は加齢に伴う変性だけでなく、スポーツや交通事故などの外傷によっても発症することが多いため、若年層から中高年層まで年齢を問わず発症リスクがあります。
一方、変形性膝関節症は半月板損傷に引き続いて起こることが多く、軟骨の摩耗が起こり痛みが悪化します。
特に中高年層のリスクが高い傾向にあります。
ただし、体重過多によって膝関節に大きな負担がかかると、若年層でも発症する可能性があるため適正体重を維持することが重要です。
| 半月板損傷 | 変形性膝関節症 | |
| 主な原因 | スポーツや事故による外傷・膝のねじれ加齢・体重過多による変性 | 加齢による軟骨の摩耗体重過多による膝関節への負担 |
| 発症年齢 | 若年層~中高年(スポーツや事故による損傷が多い) | 中高年以降(40代以降から発症しやすい) |
痛みの出方
外傷性の半月板損傷の場合、急な痛みが現れるのが特徴です。
損傷の程度が軽度であったり変性の半月板損傷では膝の違和感や引っ掛かりを感じるようになり、徐々に痛みが悪化していきます。
変形性膝関節症も、変性の半月板損傷と症状は似ていますが、持続的な鈍い痛みが続いたり、歩き始めや長時間の歩行、立ち仕事によって痛みが強くなっていく特徴が見られます。
| 半月板損傷 | 変形性膝関節症 | |
|---|---|---|
| 痛みの特徴 | 急な痛み膝の引っかかり感・ロッキング | 持続的な鈍い痛み動き始めや長時間の動作で悪化 |
| 痛みが強くなる動作 | 階段の上り下りしゃがむ・膝を捻る動作 | 立ち上がり歩行時長時間の立ち仕事 |
治療方法
治療方法は主に初期段階では保存療法、中期以降で状態が悪化している場合には手術療法が検討されます。
半月板損傷の手術には部分切除という方法もありますが、組織の一部を切除することで関節のバランスが崩れ、変形性膝関節症のリスクを高めるおそれがあります。
そのため、切除術ではなく縫合術が推奨されます。
しかし、変性断裂の場合は縫合術の適応になりにくく、部分切除術を選択することになる場合が多いため、保存療法になる場合が多いです。
| 半月板損傷 | 変形性膝関節症 | |
|---|---|---|
| 初期段階または軽度の場合の治療法 | 保存療法薬物療法理学療法士の施術体外衝撃波(集束型)再生医療(PRP・幹細胞治療・成長因子療法) など | 保存療法薬物療法理学療法士の施術ヒアルロン酸注射体外衝撃波(集束型)再生医療(PRP・幹細胞治療・成長因子療法) など |
| 中期以降または重度の場合の治療法 | 保存療法理学療法士の施術体外衝撃波(集束型)再生医療(PRP・幹細胞治療・成長因子療法) 手術療法関節鏡下半月板縫合術 |
保存療法理学療法士の施術体外衝撃波(集束型)再生医療(PRP・幹細胞治療・成長因子療法) 手術療法骨切り術人工関節置換術 |
半月板損傷の受診目安

半月板損傷は早期に治療を開始することで重症化を防げますが、病院を受診すべきか判断に迷うことも多いでしょう。
ひとつの目安として、以下の症状が見られる場合には半月板損傷の可能性が考えられるため、痛みが軽度であっても早めに整形外科を受診することがおすすめです。
- 膝に強い力が加わったり、ひねる動作の後に痛みを感じるようになった
- スポーツのときや階段を下りるときに膝が痛む
- 膝を動かしたときに引っかかる感覚がある
- 定期的に膝が腫れたり、圧迫感がある
関連記事:半月板損傷とはどんな状態?原因や症状、治療について詳しく解説!
半月板損傷でお悩みの方はイノルト整形外科まで
半月板損傷の程度はさまざまで、進行度合いや損傷の程度によっても最適な治療法は異なります。
また、そもそも膝の痛みを引き起こす疾患は半月板損傷以外にも存在するため、正確な診断には適切な検査が不可欠です。
イノルト整形外科では関節専門外来とスポーツ整形外科を設置しており、レントゲンやMRI(外部医療機関へ依頼)といった検査で正確な診断を行います。
また、近年注目されている再生医療や体外衝撃波、ハイドロリリースといった最新鋭の治療法にも対応しているため、患者様の状態に合わせた最適な治療法をご提案できます。
さらに半月板損傷はスポーツ中の事故によって起こるケースも多いため、再発を防ぐための専門的なケアや膝への負担が少ないフォームのアドバイスなども可能です。
まとめ
半月板損傷は年齢を問わず誰にでも起こり得る疾患ですが、軽度の場合は痛みも強くないため放置する患者様が少なくありません。
しかし、治療を後回しにしていると重症化し、日常生活に支障をきたすケースも出てくるでしょう。
今回ご紹介した症状や受診目安を参考に、該当する項目があった場合には早めに整形外科を受診し適切な治療を受けましょう。
股関節唇損傷とは?やってはいけないことやおすすめストレッチを紹介
日常生活における何気ない動作の中で、股関節に痛みや違和感を感じた経験はないでしょうか。
このような症状が続いている場合、股関節に何らかの異常が発生している可能性が考えられるため、なるべく早めに検査と治療を受ける必要があります。
本記事では、股関節疾患のひとつである股関節唇損傷の治療法や重症化を防ぐための注意点、治療に要する期間をご紹介します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
股関節唇損傷とは?
股関節唇損傷とは、股関節の骨頭を覆う関節唇(かんせつしん)が傷ついたり破れたりする疾患です。
関節唇は軟骨組織でできており、股関節の安定性を保つとともに、衝撃を吸収し滑らかな動きをサポートする重要な役割を果たします。
しかし、何らかの要因によって股関節に過度な力が加わると、軟骨組織が損傷し痛みを生じることがあります。
股関節唇損傷の程度はさまざまで、初期の段階では股関節の引っ掛かり感や不安定感、違和感などを覚えることが多く、やがて痛みが生じてきます。
治療をせずに放置しておくと激しい痛みを感じるようになり、やがて股関節の動きが制限され日常生活にも支障をきたすことも少なくありません。
股関節唇損傷の原因
股関節唇損傷はどういった原因で発症するのでしょうか。代表的な要因を4つご紹介します。
加齢
加齢に伴い、関節唇を構成する軟骨組織が劣化しやすくなり、その結果として股関節唇損傷につながります。
本来、軟骨組織は弾力性がありクッションの役割を果たしていますが、年齢とともに弾力性が低下していき損傷しやすくなります。
また、長年にわたって股関節に負担がかかり続けた結果、徐々に関節唇の損傷につながります。
構造上の問題
股関節の形状や構造に問題がある場合、関節唇に過剰な負荷がかかり、損傷のリスクが高まります。
股関節インピンジメント(FAI:Femoroacetabular Impingement)といわれるもので、FAIは股関節の構造異常により、大腿骨頭と寛骨臼(骨盤側の受け皿部分)が正常に動かず、関節内で衝突が生じる状態です。
この衝突が原因で、股関節唇や軟骨に損傷が起き、痛みや可動域の制限を引き起こします。
スポーツ
加齢と並んで多い要因が激しいスポーツや運動によるものです。
特に、サッカーやバスケットボールなどの激しい動きが多いスポーツでは、急な方向転換やジャンプによって股関節に衝撃が加わりやすく、関節唇を損傷する要因になりがちです。
また、野球、水泳、ダンス、バドミントン、格闘技など、股関節を繰り返し深く曲げ伸ばししたりひねる動作が多いスポーツも股関節への負担がかかりやすくリスクが大きいといわれています。
外傷
稀ですが転倒や交通事故などによって、外部から大きな衝撃が加わることも股関節唇損傷の要因となります。
加齢やスポーツによる損傷は徐々に痛みが増してくることが多いですが、外傷が原因の場合には直後に強い痛みを伴うことが多くなります。
関連記事:膝関節の痛みの原因|痛みを和らげるセルフケアや病院の受診目安
股関節唇損傷でやってはいけないこと
股関節唇損傷を悪化させないためには、日常生活の何気ない動作にも注意が必要です。特に、以下の動きは避けるよう心がけましょう。
繰り返すしゃがみ込み
深くしゃがむ行動は、股関節に負担をかけ、関節唇の損傷を悪化させる可能性があります。
特に繰り返し長期間続けることで症状を悪化させるリスクが高まるため、痛みを感じるようであれば無理をせずしゃがむ動作を減らしましょう。
無理なジャンプや急なダッシュ
高い場所からのジャンプや急なダッシュは、股関節に強い衝撃を与え損傷を悪化させる恐れがあります。
特に、準備運動を怠ったり運動の習慣がない人ほどリスクが高まるため注意が必要です。
股関節をねじる動作
水泳の平泳ぎやテニスの回転動作など、股関節を強くねじる動きは関節唇に負担をかけやすいため注意が必要です。
これらの動作を行う場合は、はじめから思いっきり行わず、まずはゆっくりと動かしながら痛みが出ないように関節に負担がかかりにくい正しいフォームを身につけていきましょう。
深いスクワットや負荷の高い筋トレ
深くしゃがむスクワットや重いウエイトを持ち上げる筋力トレーニングは、股関節唇に過剰な負担をかける可能性があります。
そのため、まずは軽めのトレーニングからスタートし、徐々に負荷を上げていきましょう。
無理な可動域を求めるストレッチ
開脚や大きく足を広げる動作など、関節の限界を超えたストレッチは損傷を悪化させるリスクがあります。
ストレッチを行う際には心地よいと感じる範囲内に収め、痛みを感じた場合には無理に動かさないことが大切です。
片足に重心をかけた姿勢
片足に体重をかけ続ける立ち方や歩き方は、股関節にアンバランスな負担をかけます。
日常生活における直立の姿勢や歩行では、体重を均等に分散させることを意識しましょう。
関連記事:変形性膝関節症の主な原因は?女性に多い理由や若年層の発症についても解説
股関節唇損傷におすすめストレッチ
股関節唇損傷の予防やリハビリにおいては、股関節周囲の筋肉を無理のない範囲でほぐすストレッチが効果的です。
腸腰筋のストレッチ
腸腰筋は股関節のスムーズな動きに重要な役割を果たしているため、この筋肉を柔らかくすることで股関節の負担軽減が期待できます。
- 床に片膝立ちの姿勢を取る(前脚は90度に曲げる)
- 後ろ側の脚を後方に伸ばし、骨盤を前に押し出す
- 股関節の前側が伸びているのを感じながら、20~30秒間キープ
- 左右の脚を替えて1〜3を繰り返す
ポイントとしては、2の段階で脚を後方に伸ばす際に、骨盤を捻ったり横に向いたりするのではなく、真っ直ぐ前方に押し出すことを意識しましょう。
おしりのストレッチ
お尻には太ももから伸びる大きな筋肉が集中しており、股関節を安定的に支える役割があることから、定期的にストレッチを行うことで股関節の機能改善が期待できます。
- 仰向けの状態で左足を伸ばし、右膝を立ててクロスさせる(足を組むような姿勢)
- 右足を左側にゆっくり倒す
- お尻や太ももの付け根が伸びるのを感じながら、20~30秒間キープ
- 左右の脚を替えて1〜3を繰り返す
足を倒す際に体を捻る姿勢になるため、無理をせずゆっくりと行いましょう。痛みを感じた場合は無理をせず、心地よいと感じる範囲に留めておきます。
股関節唇損傷の治療方法
股関節唇損傷の治療は保存療法から外科的な治療、再生医療などさまざまな選択肢があります。
薬物療法
日常生活へ支障をきたさないよう、痛みや炎症を抑えるために行われるのが薬物療法です。
主にロキソニンなどの痛み止めや湿布が処方されることが多く、理学療法士の施術などを併用するケースが一般的です。
理学療法士の施術
ストレッチや筋力トレーニングなどの理学療法士の施術も代表的な治療方法のひとつです。
股関節周囲の筋力バランスを整えることで症状の改善が期待されますが、誤った運動は股関節への負担を増大させ症状の悪化を招くリスクもあるため、理学療法士の指導を受けながら行う必要があります。
この治療法を行うことで痛みは改善するケースが多いです。
ヒアルロン酸注入
股関節の変形によって摩擦が生じ、それが原因で炎症や痛みを発症している場合にはヒアルロン酸を注入し潤滑性を高め、症状を緩和することができます。
ただし、ヒアルロン酸は徐々に体内に吸収されていくため定期的な注入が必要であるほか、根本的な治療法ともいえません。
体外衝撃波治療
体外衝撃波治療とは、関節部位に特殊な衝撃波を照射し自然治癒力を高める治療法です。
衝撃波には痛みを軽減する効果があるほか、複数の成長因子を産出し損傷した組織の修復を促す効果もあります。
体外衝撃波治療には広範囲に照射する拡散型と、ピンポイントに照射する集束型の2タイプがあり、股関節唇損傷の治療には集束型が用いられることが多いです。
手術療法
損傷の程度が大きく、上記でご紹介した治療法で回復が見込めない場合には、手術療法が選択されるケースもあります。
損傷や関節唇を縫合したり、せり出して関節唇損傷の原因となっている骨の一部を削る手術を行います。
ただし、手術療法は患者様への負担が大きく、入院やリハビリにも時間を要するため、最終的な治療の選択肢として提示されるケースがほとんどです。
再生医療
手術療法に換わる新たな治療法として注目されているのが再生医療です。
患者様自身の脂肪や骨髄から採取した幹細胞を使用し、損傷部位の再生を図る幹細胞治療や、血液から抽出した成分を再び体内に注入し組織修復を促す成長因子療法などがあります。
自己治癒力を高め関節唇の修復を促進する革新的な治療法ではありますが、保険適用外となるため治療費が保険診療と比べると高額になります。
また、関節の損傷度合いによっては再生医療でも回復が難しいケースもあり、そのような場合には手術療法が選択されることもあります。
手術で関節唇を縫合した場合は、術後に再生医療を行うことでより手術の治療効果が高まることが期待できます。
股関節唇損傷はどのくらいで治る?
股関節唇を損傷した場合、治療が完了し日常生活に戻るまではどの程度の期間を要するのでしょうか。
損傷の程度や治療法、患者様の年齢や体質などによっても治療期間は変わってきますが、軽症の場合は数週間から数ヶ月程度の保存療法を行いながら徐々に日常生活に復帰していきます。
一方、重度の損傷で手術療法が必要な場合には、1~2週間程度の入院の後、少なくとも数カ月のリハビリを継続する必要があります。
また、股関節の機能が回復し通常の生活に戻るためには、数ヶ月から1年程度のリハビリやトレーニング期間を要することもあります。
股関節の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで
股関節に違和感や痛みがある場合、今回ご紹介した股関節唇損傷の可能性が考えられます。
しかし、これ以外にもさまざまな股関節の疾患があり、正確な診断を行うためには医療機関で精密検査を受ける必要があります。
また、症状や関節の状態によっても適切な治療法は異なり、特に今回ご紹介した体外衝撃波治療や再生医療、手術療法などは対応できる医療機関も限られています。
股関節の状態を正確に把握し、幅広い選択肢の中から自分に合った治療法を選びたいという場合には、イノルト整形外科へお気軽にご相談ください。
イノルト整形外科では関節専門外来を設置しており、痛みの原因を正確に診断し最適な治療法を提案させていただきます。
最新の検査機器や医療設備も完備しており、体外衝撃波治療や再生医療などにも対応できます。
関連記事:体外衝撃波治療の効果とデメリットは?|適応疾患や頻度についても解説
まとめ
股関節唇損傷は加齢や激しい運動、外傷などが原因で発症することが多く、痛みを放置しておくと関節が変形し可動域が制限される可能性もあります。
重症化を防ぐためにも、股関節に痛みや違和感がある場合には信頼できる医療機関を受診し早めに治療をスタートすることが大切です。
股関節唇損傷の治療法は理学療法士の施術や薬物療法、手術療法などが一般的ですが、近年では体外衝撃波治療や再生医療といった新たな治療法も確立されています。
幅広い選択肢の中から自分に合った治療法を選びたいという場合には、ぜひイノルト整形外科へご相談ください。
膝が痛い時の対処法は?やってはいけないことや受診のポイントを解説
膝の痛みは多くの人が抱える悩みであり、年齢や生活習慣、疾患などさまざまな原因が考えられます。
痛みがあるのに治療をせず放置しておくと重症化し、日常生活にさまざまな支障をきたす可能性も出てきます。
そこで本記事では、膝が痛い時にどういった対処をすれば良いのか、日常生活で注意すべき動作やセルフケア方法について詳しく解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
膝が痛い時の対処法
膝に痛みがある場合、症状や膝の状態に合わせて正しい対処をとらないと悪化するおそれがあります。
対処法の見極めにあたって重要なのが、膝が熱をもっていたり腫れていないかという点です。
膝が熱を持っている・腫れている場合
スポーツや事故などによってケガをすると、膝の周辺を触ったときに熱っぽく感じたり、腫れたりすることがあります。
このような症状が見られる場合、炎症を起こしている可能性が高いため、まずは患部を安静にして冷やして炎症を鎮めることが重要です。
氷のうやアイスパックなどをタオルで包み、患部に当てて熱や腫れが引くまで様子を見ましょう。
ちなみに、氷のうやアイスパックを患部に直接長時間当ててしまうと凍傷の危険性があるため、必ずタオルなどに包んで使用してください。
膝に熱も腫れもない場合
膝に熱や腫れが見られず、慢性的な痛みが現れることもあります。このような場合には、膝の血行を高める必要があるため、患部を温めることが大切です。
膝を温めるためにはさまざまな方法がありますが、中でも効果的なのが入浴です。
局所的に膝を温めるよりも全身の血行が良くなり、痛みを緩和しやすくなります。
また、入浴しながら患部をマッサージすることで、筋肉がほぐれ、さらなる血行改善効果が期待できます。
関連記事:膝の痛みは自分で治せる?膝が痛む原因とセルフケア方法を解説
膝が痛む原因となる疾患
膝に激しい痛みが現れたり、慢性的な痛みが続く場合には、以下のような疾患の可能性も考えられます。
変形性膝関節症
変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨がすり減り、末期になると骨同士が直接接触するようになることで痛みや腫れが生じる疾患です。
加齢とともに膝関節への負担が徐々に蓄積していくことで発症するケースもあれば、運動のしすぎや体重の増加が原因で発症するケースもあります。
初期の段階では膝の違和感や軽い痛みが現れ、安静時には症状が収まることが多いですが、進行すると安静時にも痛みを感じるようになり、日常生活にも支障をきたすリスクがあります。
半月板損傷
半月板損傷とは、膝関節のクッションの役割を果たしている半月板という組織が損傷する疾患のことです。
スポーツや激しい動作によって、急な方向転換や転倒の際に発症することもありますが、中高年ではしゃがんだ立ったりくらいこ軽微な動作でも簡単に損傷してしまうことが多く、強い痛みを生じます。
軽度の半月板損傷であれば膝の軽い痛みや引っかかる感じやわずかな腫れを伴うことが多いですが、治療をせず放置しておくと重症化し激しい痛みを伴うこともあります。
関節リウマチ
関節リウマチとは、原因不明の免疫系の異常により関節の炎症が慢性的に続く自己免疫疾患です。
膝に限らず全身のさまざまな関節が炎症を起こしますが多くは手の指や手首に痛みや腫れ、こわばりなどの症状が見られます。
関節リウマチが発症する明確な原因は分かっていませんが、男性よりも女性の発症リスクが高いほか、遺伝的要因や喫煙や飲酒などの生活習慣も可能性のひとつとして考えられます。
なお、関節リウマチは進行すると関節が変形するリスクもあるため、早期の治療が大切です。
鵞足炎
鵞足炎(がそくえん)とは、膝の内側にある「鵞足」という組織に炎症が生じる疾患です。
ランニングやジャンプなど過度に負荷がかかることで発症することが多く、膝の内側に痛みや腫れが生じます。
また、安静時には痛みを感じなくても、歩行や膝の曲げ伸ばしなどの際に痛みが強くなるのも特徴です。
半月板損傷や変形性関節症と症状が似ているのでしばしば間違って診断されていることもあります。
その他の疾患
上記以外にも、外傷や膝の酷使によって滑液包が炎症を起こす滑液包炎や、尿酸値が高まることで発症する痛風、ピロリン酸カルシウムなどの結晶が原因で発症する偽痛風などの疾患も可能性として考えられます。
膝が痛い時にやってはいけないこと
膝に痛みが現れたとき、何気ない日常生活の動作が原因で重症化する可能性があります。どういったことに注意すべきなのでしょうか。
激しい運動・トレーニング
膝が痛い時に激しい運動やハードなトレーニングを行うと、症状が悪化する恐れがあるため安静を心がけることが大切です。
たとえば、長距離のジョギングやスクワットなど、ジャンプ動作の多いバスケットボールやバレーボールなどは膝への負担が大きいため避けましょう。
筋力を維持するためには適度な運動も必要ですが、医師や理学療法士の指導のもと安全にリハビリを行うことが重要です。
サイズの合わない靴を履く
サイズの合わない靴は無意識のうちに不自然な姿勢になり、膝に過度な負担がかかり痛みを悪化させる要因となります。
また、クッション性がない靴やヒールの高い靴も膝に衝撃がかかりやすいため、できるだけ避けましょう。
和式での生活環境
和式トイレの使用や正座など、和式の生活環境は膝にかかる負担が大きくなりがちで、痛みを悪化させる原因になります。
外出先では洋式トイレを使用したり、自宅の中では畳の上に正座ではなくテーブルと椅子を使用するなど、膝に無理な負担をかけない生活を心がけましょう。
重い物の上げ下げ
過度な負荷をかけた筋力トレーニングや力仕事など、重い物を持ち上げる動作は膝にかかる負担も大きく、無理をすると痛みが増すことがあります。
膝の痛みが落ち着くまではこのような動作は避け、トレーニングや仕事を再開する際においても、膝に負担をかけずに持ち上げるフォームを意識することが重要です。
具体的には、重量物を持ち上げる際には膝ではなく腰を中心に動かすよう意識し、無理な姿勢は避けるようにしましょう。
体を冷やす
慢性的な膝の痛みがある場合には、体を冷やすことで血行が悪くなり、症状が悪化することがあります。
そのため、できるだけ毎日湯船につかって体を温め、膝を重点的にマッサージして血行を改善するように心がけましょう。
関連記事:膝の皿の上が痛い原因とは?突然の痛みや、疾患や治し方について解説
膝が痛い時に病院受診は必要?受診の目安とは
膝が痛いといっても症状には個人差があり、病院を受診すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
入浴で体を温めたり、マッサージをすることで一時的に症状を緩和することもできますが、根本的な治療をせずに放置しておくと状態が悪化し、変形性膝関節症などの疾患につながる可能性もあります。
このようなリスクを低減するためにも、以下のような症状・状態の方は早めに病院を受診することがおすすめです。
膝に熱や腫れが見られる
スポーツや事故な怪我によって膝を負傷し、熱や腫れが見られる場合、まずは応急処置として患部を冷やすことが大切です。
ただし、一時的に炎症は収まったとしても靭帯や骨などを負傷している可能性もあるため、できるだけ早めに病院を受診し精密検査を受ける必要があります。
慢性的に膝が痛い
慢性的な膝の痛みが現れる場合、変形性膝関節症や半月板損傷、関節リウマチ、痛風といった疾患の可能性もあります。
痛みの原因をはっきりさせないと治療法も疾患ごとに全く異なるため、まずは病院を受診し検査を受けることが大切です。
立ち上がるときや歩行時に膝が痛い
安静時には痛みを感じないものの、椅子から立ち上がるときや歩いているときに膝が痛い場合には、変形性膝関節症や滑液包炎などの初期症状が疑われます。
特に変形性膝関節症の場合、治療を放置しておくと関節そのものが変形し本来の機能を果たせなくなる可能性もあるため、早めに病院を受診し検査と治療をスタートする必要があるでしょう。
膝の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで
上記の「膝が痛む原因となる疾患」でご紹介した疾患はあくまでも一例であり、これ以外にもさまざまな疾患が存在します。
膝の痛みを根本から解決するためには、精度の高い検査と専門医による正確な診断が不可欠です。
また、膝の状態や疾患によっても治療法は異なり、近年では痛みの少ない新たな治療法も確立されていますが、全ての整形外科クリニックが対応できるとは限りません。
イノルト整形外科では関節専門外来を設置しており、レントゲンや超音波、MRIといった高度な機器による精密検査が可能です。
また、多くの整形外科クリニックで用いられている薬物療法や装具療法のほか、理学療法士のリハビリ、再生医療や体外衝撃波治療といった最新の治療法にも対応。
患者様の状態や要望に応じて最適な治療方針を提案させていただきます。
まとめ
膝の痛みはさまざまな原因が考えられ、治療をせずに放置すると症状が悪化し日常生活にも支障をきたす可能性があります。
そのため、膝が痛い時には過度な負担をかける動作を避け、正しいケアや生活習慣の改善が必要です。
セルフケアとしては入浴やマッサージなどが効果的ですが、痛みが続く場合には早めに病院を受診し適切な治療を受けることも大切です。
膝の痛みは自分で治せる?膝が痛む原因とセルフケア方法を解説
治療の開始が遅れると重症化していき、変形性膝関節症や半月板損傷といった疾患につながる可能性もあるため、信頼できる整形外科クリニックに診てもらいましょう。
さまざまな関節の中でも膝関節は特に負担がかかりやすく、痛みを感じることが多い部位のひとつです。
しかし、痛みの原因はさまざまであり、症状の現れ方も個人差があります。
整形外科を受診したほうが良いか分からない、あるいは仕事が忙しく通院の時間が確保できないという方も多いでしょう。
そのような場合、膝の痛みは自分で治せるものなのでしょうか。
本記事では、膝の痛みに効くセルフケアの一例や、整形外科を受診すべき目安などを詳しくご紹介します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
膝が痛む原因
膝に痛みが生じるのはさまざまな原因が考えられます。代表的な7つの原因をご紹介しましょう。
加齢
年齢を重ねると膝関節の軟骨が徐々に摩耗していきます。
軟骨はクッションの役割を果たしており、これが摩耗すると関節内で骨同士がこすれ、痛みや炎症が生じやすくなります。
また、加齢とともに筋力も低下しやすくなりますが、これによって膝関節を安定的に支えることが難しくなり、膝への負担が増大し痛みにつながることもあります。
膝の酷使
スポーツや力仕事で日常的に膝を酷使していると、関節に負担がかかり炎症や損傷が起こりやすくなります。
特に、ジャンプや階段の上り下りなどのように同じ動作を繰り返していると、軟骨や靭帯などの特定の部位にのみダメージが蓄積され、痛みが慢性化することもあります。
運動不足
運動のしすぎだけでなく、極端な運動不足も膝を痛める原因になることがあります。
膝を動かす頻度が少ないと、膝関節周辺の筋力が低下し関節への負担が増えていきます。
その結果、歩行や階段の上り下り、しゃがむといった日常の動作でも膝への負担が大きくなり、痛みを引き起こしやすくなります。
肥満
膝関節に過度な負担がかかる原因になりがちなのが、体重の増加です。
膝関節は体重を支える重要な役割を果たしており、特に歩行や階段の上り下りなどの際に負担がかかります。
体重が増えるほど膝関節にかかる負担も大きくなり、同じ運動量でも早いペースで軟骨がすり減っていき、痛みを感じやすくなるのです。
O脚やX脚
O脚やX脚といった脚の変形は、膝関節に不均等な負担をかける原因になります。
その結果、O脚なら膝の内側、X脚なら膝の外側の軟骨が磨耗しやすくなり、痛みはもちろんのこと関節そのものが変形が進行するリスクも高まります。
合わない靴の着用
足の形やサイズに合わない靴を履いていると、無意識のうちに膝関節をかばうような歩き方になります。
これが長期間続くと、膝関節の一部分にのみ負担が集中し痛みが生じやすくなります。
変形性膝関節症・半月板損傷
膝の違和感や痛みを放置しておくと、半月板損傷や軟骨損傷から変形性膝関節症を発症しさらに強い痛みを引き起こしたり、最悪の場合歩行が困難になるほど重症化するおそれもあります。
また、スポーツや事故などによって膝に外傷を負うと、それが原因で半月板が損傷し強い膝の痛みを引き起こすこともあります。
膝の痛みは自分で治せる?セルフケア方法
膝の痛みが軽度であれば、適切な処置を施すことで症状を緩和できる可能性もあります。代表的なセルフケアの方法をご紹介しましょう。
安静にする
膝に違和感や痛みがある場合には、無理に動かさず痛みが引くまで安静にすることが大切です。
痛みを我慢して激しい運動や力仕事をすると、膝にさらなる負担がかかり症状を悪化させる可能性があります。
日常生活の範囲内での歩行程度であれば問題ありませんが、長時間のウォーキングや体重を掛ける筋力トレーニング、力仕事などは避けましょう。
ただし、下肢の筋力は落とさない方が良いので、体重を掛けないで行う筋力トレーニングは必要です。
ストレッチ
膝関節の安定感を保つために、重要な役割を果たしているのが太ももの筋肉です。
ストレッチを行うことで太ももから膝にかけての筋肉が伸ばされ、膝関節に掛かる負担を軽減し痛みの改善に役立ちます。
マッサージ
ストレッチと合わせてマッサージも行うことで筋肉が柔らかくなり、膝関節の安定感を保てるようになります。
- 床に座った状態で足を伸ばす
- 膝関節から太ももにかけて、手のひらで押し込むようにマッサージをする
- 痛みを感じる場所は力を入れすぎず、心地よいと感じる程度に押す
筋トレ
安静にしている時間が長いと膝まわりの筋力が低下し、体重を支えきれなくなることもあります。
痛みが引いてきたら少しずつトレーニングを行い、筋力アップを目指しましょう。
膝の痛みは自分で治せる?おすすめの運動
膝の痛みを軽減するためにはセルフケアが有効ですが、基本として押さえておきたい運動やストレッチの手順をご紹介しましょう。
太ももの筋力を鍛える運動
先述の通り、膝関節は太ももの筋肉によって支えられているため、痛みの予防・軽減には大腿四頭筋や中殿筋を鍛えるトレーニングが効果的です。
大腿四頭筋のトレーニング
- 仰向けになる
- 膝の下に枕を置く
- 膝の裏側を下に押し込むように力を入れる
中殿筋のトレーニング
- 横向きに寝る
- 上の足(右方向に寝た場合は左足)を伸ばした状態でゆっくり上げる
- ゆっくり下ろす
いずれのトレーニングも横になった状態で行えるため、体重によって膝に過度な負担をかけることなく筋力アップが可能です。
膝の曲げ伸ばしのストレッチ
筋肉が低下したり柔軟性が失われたりすると、膝関節の安定性が失われ痛みが悪化します。
そこで、膝のストレッチを習慣づけることも痛みの軽減につながります。
膝のストレッチ
- 床に座る
- 片側の足を伸ばした状態で反対側の足は曲げる
- 曲げた足を両手で抱え、手前にゆっくりと引き寄せる
- 左右の足を替えて同様に行う
お皿のストレッチ
運動の習慣がない方が急に運動を始めると、膝の靭帯や筋肉を痛める原因になります。そこで、膝の皿とよばれる膝蓋骨周辺のストレッチも効果的です。
- 椅子に座った状態で足を伸ばし、足の力を抜く
- 両手の親指で膝の皿周辺を上下左右に動かす
- 左右の足を替えて同様に行う
日常でできる膝の痛みを予防する方法
普段の何気ない生活習慣が膝の痛みを悪化させる原因になっていることも少なくありません。日常生活のなかでできる対策をいくつかご紹介しましょう。
歩き方を見直す
人によっては歩き方の癖がついていることもありますが、たとえば猫背や前かがみの姿勢になりすぎているとバランスが崩れ、膝にも大きな負担がかかります。
そのため、まずは正しい歩き方を意識してみましょう。
正しい歩き方のポイント
- 背筋を伸ばし、あごを引いて歩く
- 視線は5m先の地面を見るイメージ
- 適度な歩幅を維持する(着地時に膝が軽く曲がる程度)
- かかと→親指の付け根→つま先 の順番で体重を移動させるよう意識する
- 足の動きに合わせて腕を振る
肥満を予防
体重が増加することで膝にかかる負担が増大し、関節を痛める直接的な原因になり得ます。
また、体重が増加すると体が重く感じ、徒歩や階段の上り下りなどの日常的な運動も敬遠しがちになります。
その結果、さらなる体重の増加を招き膝への負担も増大するという悪循環に陥ってしまいます。
このような事態を防ぐためにも、摂取カロリーを考えた食事を心がけるなどして肥満を予防しましょう。
適度な運動
運動不足に陥ると筋力が低下し、膝関節の安定性が失われます。また、先述した肥満にも直結し、膝への負担が増大する原因にもなりかねません。
運動の習慣がない方の場合、いきなり長距離のウォーキングやジョギングは辛く感じてしまうものです。
そのため、まずは無理のない範囲でスタートし、少しずつ距離を伸ばしていきましょう。
また、膝の痛みで歩いたり走ったりが難しい場合には、水泳や自転車をこぐマシーンのように膝に負担がかからない運動を試してみるのもおすすめです。
過度な運動は避ける
運動によって筋力を維持することは重要ですが、ハードなトレーニングは膝への負担が増大し逆効果になる危険もあります。
特に、重いものを持った状態での膝の曲げ伸ばしや、ジャンプ動作の繰り返しなどは膝への負担が大きいため注意しましょう。
関連記事:膝の痛みの場所別原因まとめ|突然ズキズキ痛むのは危険?
膝の痛みで整形外科を受診する目安
一口に膝の痛みといっても、症状の程度や状態はさまざまです。
たとえば、一時的な痛みや軽度の痛み、膝の違和感などが見られる場合には、今回ご紹介したセルフケアで改善できる可能性もあるでしょう。
しかし、外傷によって膝に強い痛みを感じる場合や、セルフケアをしても痛みが緩和せず悪化している場合などは、変形性膝関節症や半月板損傷などを発症している可能性もあるため、早急に整形外科を受診することがおすすめです。
また、セルフケアによって一時的に症状は改善したものの、日数が経過すると再び症状が現れるような場合においても、整形外科を受診することで再発を防げるようになります。
膝の痛みでお悩みの方はイノルト整形外科まで
膝関節の痛みはさまざまな原因が考えられるため、高度な検査機器や設備が充実した信頼できる整形外科を選ぶことが大切です。
膝関節の治療といえば、従来は薬物療法や物理療法、装具療法などが定番でしたが、近年では医療技術の発達により再生医療や体外衝撃波治療といった新しい治療法も登場しています。
幅広い選択肢の中から自分に合った治療法を選ぶという意味でも、これらに対応できる整形外科が理想的といえるでしょう。
イノルト整形外科では関節専門外来を設置しており、患者様の状態や要望に応じて上記でご紹介した幅広い治療法の中から最適なプランをご提案させていただきます。
「他院で治療を受けたものの、痛みが引かない」「早期回復が期待できる治療法を選択したい」とお考えの方は、まずはイノルト整形外科までお気軽にご相談ください。
関連記事:膝の裏が痛い!「ピキッ」という鋭い痛みの原因や治し方を解説
まとめ
膝の痛みの現れ方はさまざまで、特に症状が軽度の場合自分で治したいと考える方も多いでしょう。
ストレッチやマッサージなどさまざまなセルフケアの方法はありますが、これらを行っても症状が改善しない場合には早めに整形外科を受診することがおすすめです。
治療の開始が遅れると重症化していき、変形性膝関節症や半月板損傷といった疾患につながる可能性もあるため、信頼できる整形外科クリニックに診てもらいましょう。
変形性膝関節症の主な原因は?女性に多い理由や若年層の発症についても解説
信頼性が高く多様な治療法に対応した整形外科クリニックをお探しの方は、ぜひ一度イノルト整形外科へご相談ください。
加齢や体重の増加などによって膝に痛みが現れた場合、変形性膝関節症を発症している可能性が考えられます。
一般的に変形性膝関節症は高齢者に多い疾患といわれていますが、20代や30代といった若年層も発症するケースはあります。
また、男性に比べて女性の発症割合も高く、気になる症状が現れた場合には早めに治療をスタートさせることも大切です。
本記事では、変形性膝関節症の主な発症原因について詳しく解説していきます。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
変形性膝関節症とは?
変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨がすり減ることで関節内に炎症や痛みが現れる疾患です。
ヒトの関節内部には滑膜とよばれる組織があり、関節のスムーズな動きをサポートしています。
しかし、軟骨がすり減ると、その破片の一部が滑膜を刺激し、これが原因で滑膜が炎症を起こし、その結果を引き起こします。
また、炎症が長期化すると骨に骨棘(こつきょく)という棘(とげ)が徐々にできてきて、これらがまた滑膜を刺激することで炎症が悪化するという負のスパイラルが起きやすくなります。
ただし、変形性膝関節症ははじめから激しい痛みを伴うとは限らず、特に初期段階では軽い違和感を覚える程度というケースも少なくありません。
しかし、正しい治療を行うことなく長期間放置しておくと、歩行が困難になるほど激しい痛みが生じたり、膝関節の形が変形し曲げ伸ばしが困難になることもあるのです。
関連記事:変形性膝関節症の治し方とは|痛いのに放っておくとどうなる?
変形性膝関節症の主な原因
変形性膝関節症が発症する直接的な原因は膝関節の軟骨がすり減ることですが、その引き金となる要因は何なのでしょうか。代表的な原因をご紹介します。
加齢
年齢を重ねていくと、長い歳月をかけて関節にかかる負担が徐々に蓄積されていき、軟骨もすり減っていきます。
その結果、激しいスポーツや重労働をしていなかったとしても変形性膝関節症を発症するリスクが自然と高まっていくのです。
筋力の低下
加齢はもちろんのこと、運動の習慣がなかったり、長期の入院などで体を動かす機会が極端に減ってしまうと筋力が低下していきます。
その結果、膝関節の安定を保てなくなり、関節に無理な力が加わることで軟骨が摩耗し変形性膝関節症を発症しやすくなります。
体重過多
体重が増加すると膝にかかる負担も増大し、体重を支えきれなくなります。
また、運動不足が続くと体重は増加しているのに筋力は低下し、膝関節にかかる負担はさらに大きくなります。
このような理由から、肥満体型の人ほど変形性膝関節症の発症リスクは高い傾向にあります。
O脚・X脚
直立の姿勢をとったとき、通常であれば太ももから膝、つま先にかけて僅かにX脚になっているのが正常になります。
しかし、生まれつきの骨格や筋力低下、ケガの後遺症など、さまざまな原因によってO脚やX脚になることもあります。
その結果、膝関節の一部に負荷が偏ってしまい内側もしくは外側の変形性膝関節症の発症原因となります。
日本人の場合ほとんどのケースで、O脚になりがちなので内側の変形性膝関節症に悩まされることになります。
事故やスポーツによる損傷
交通事故やスポーツなどによって外傷を負った場合、膝関節の靱帯や半月板や軟骨が損傷され、若くして変形性膝関節症を発症してしまうことがあります。
また、ケガを治療し一時的に痛みはなくなったとしても、軟骨や半月板や靱帯の損傷は修復しておらず、しばらく期間が経過した後に変形性膝関節症を発症するケースも少なくありません。
変形性膝関節症の患者数に女性が多い理由
変形性膝関節症は男性に比べて女性が発症する傾向が見られますが、それはなぜなのでしょうか。考えられる2つの原因について解説します。
女性ホルモンの影響
女性の場合、エストロゲンとよばれる女性ホルモンの一種が軟骨の保護に重要な役割を果たしています。
しかし、閉経を迎える50代頃になるとエストロゲンの分泌量は大幅に減少します。
それに伴い関節軟骨などの保護機能の低下が要因の一つで、これにより膝関節の機能が低下し変形性膝関節症を発症しやすくなると考えられています。
筋肉量
筋肉は関節の安定性を高める重要な役割を果たしていますが、もともと女性は男性にくらべて筋肉量が少ない傾向にあります。
筋力がさらに低下することにより膝関節の安定性が失われ、変形性膝関節症を発症しやすくなるのです。
変形性膝関節症は若い人でも発症する?原因は?
変形性膝関節症は若年層よりも中高年者の発症割合が高いですが、20代や30代でも発症するケースはゼロではありません。
たとえば、発症原因としてご紹介したスポーツや事故によるケガに加え、体重過多に陥ると、膝関節が体重を支えきれなくなり変形性膝関節症を発症するリスクが急激に高まります。
また、遺伝的なO脚やX脚が原因となり、それが変形性膝関節症を発症する引き金になることもあるでしょう。
この他にも、激しいスポーツや肉体労働など膝にかかる大きな負担が原因になることも少なくありません。
関連記事:変形性股関節症の治し方はある?やってはいけないことや負担をかけない寝方を紹介
変形性膝関節症の症状
一口に変形性膝関節症といっても、疾患の進行度によっても現れる症状はわずかに異なります。
今回は、初期段階に見られる症状から末期に至るまでの症状に分けてご紹介しましょう。
初期症状
変形性膝関節症の発症間もない初期段階では、以下のような症状が多く見られます。
- 膝の違和感(突っかかり感・突っ張り感)
- 立ち上がったときの軽い痛み など
一時的な痛みを感じたとしても時間が経過すれば症状が緩和されるため、初期段階では日常生活に支障をきたすほどではありません。
また、特に痛みは感じず膝の違和感が現れるというケースも多くあります。
中期症状
初期症状が現れた後、特に治療をせずに放置しておくと、以下のような中期症状が現れることがあります。
- しゃがんだり、立ったりする時に膝が痛む
- 階段の上り下りで明らかに痛い
- 正座が痛みでしにくい など
さまざまな動作に痛みを伴うようになり、日常生活にも少しずつ影響が出始めるのが中期段階です。
また、関節内に水が溜まることで膝を曲げたときに強いハリを感じるようになります。
その結果、可動域が制限され正座ができなかったり、足の曲げ伸ばしが辛く感じるようになります。
末期症状
自覚症状があるにもかかわらず、長期間にわたって変形性膝関節症の治療をせず放置しておくと以下のような末期症状が現れることもあります。
- 通常の歩行や階段の上り下りができない
- 膝関節の変形(顕著なO脚またはX脚)
- 膝を伸ばせない、曲げられない
末期の状態になると、自力での歩行が困難になるなど日常生活がままならないことも少なくありません。
変形性膝関節症の治療方法
変形性膝関節症を発症した場合、症状の程度や進行状況によってさまざまな治療法が選択されます。代表的な治療法をいくつかご紹介しましょう。
薬物療法
強い痛みや炎症が見られる場合には、症状を軽減するために痛み止めの飲み薬や湿布などの外用薬やステロイド注射などが使用されます。
ただし、最近ではステロイドは長期的なデメリットや糖尿病などの副作用の問題であまり膝関節には打つことは推奨されていません。
また、比較的軽い症状であれば、膝関節内にヒアルロン酸を注入することで関節の滑らかな動きをサポートし、症状を緩和できる場合もあります。
理学療法士によるリハビリテーション
多くの場合、筋力や柔軟性の低下、姿勢の悪化を伴う関節の機能の低下を認めるため、理学療法士によるリハビリテーションを行うことで筋力を強化し、関節の安定性を取り戻すことができます。
特に膝に強い痛みがあると、自然と膝をかばうような動作をとるため筋力が低下したり姿勢が悪くなったりしやすくなります。
膝関節へ無理な負担をかけずに筋力をつけるためにも、リハビリテーションは基本的な治療法のひとつといえます。
体外衝撃波治療
体外衝撃波治療とは、衝撃波というエネルギー波を患部に照射することで、損傷した組織の修復を促し痛みや炎症を強力に改善しやすい治療法です。
手術のように入院やリハビリの必要がなく、施術時間も短いため患者様の身体的負担は少なくて済みます。
本来の体外衝撃波治療とは集束型の治療器をいい、比較的普及している拡散型の治療器は正式には圧力波治療器といい、正確には体外衝撃波治療とは異なります。
集束型も拡散型も、整形外科における治療法としては比較的新しく、専用の治療機器や設備も必要なため対応できるクリニックはごく一部に限られています。
モヤモヤ血管治療
モヤモヤ血管治療とは、変形性膝関節症により炎症が起きている炎症由来の細い動脈に薬剤を流すことで炎症を起こしている血管を詰まらせ、炎症に伴う痛みの大幅な緩和を期待できます。
血管の選定や細い血管内へのエコーを見ながらの注射は整形外科医でもごく一部の医師しかできない技術になりますので、医療機関の選択はとても重要なものになります。
ハイドロリリース治療
ハイドロリリースとは筋膜リリースともよばれ、薬液を注入し癒着した筋膜を剥がす治療法です。
痛みやコリなどを緩和する治療法として注目されており、変形性膝関節症においては筋筋膜性の痛みが見られる場合に顕著な改善効果が期待できます。
なお、ハイドロリリース治療はエコー画像を確認しながら筋膜の癒着部位を見極める必要があるため、治療実績やノウハウが豊富なクリニックを選ぶことが大切です。
再生医療
最新の治療法として近年注目されているのが再生医療です。
患者様から取り出した血液や脂肪に含まれる組織を培養する幹細胞治療、もしくは血液中の組織を修復させる物質を抽出するPRP療法・成長因子療法、それを患部に注入することで損傷した部位の再生を図る治療法です。
幹細胞治療やPRP療法などさまざまな治療法があり、いずれも最小限の通院で済むため日常生活への影響もほとんどありません。
ただし、再生医療には専門的な知見とノウハウが求められることもあり、対応できるクリニックも一部に限られています。
また、基本的には再生医療は自由診療となるため健康保険が適用されず、治療費も保険診療と比べると高額になります。
手術療法
変形性膝関節症が重症化し軟骨が著しく損傷している場合や、他の治療方法で満足のいく結果が得られない場合には手術が選択されることがあります。
変形性膝関節症の程度や年齢に合わせて、骨切り術もしくは人工膝関節置換術などの方法があり、入院やリハビリ期間は必要であるものの優れた治療効果が期待できます。
関連記事:PRP療法の注射が膝や股関節に効果的な理由とは?副作用はある?
変形性膝関節症でお悩みの方はイノルト整形外科まで
変形性膝関節症の原因や症状の程度はさまざまで、早期回復を図るためには信頼性が高く様々な治療法に対応できるクリニックを選ぶことが大切です。
今回ご紹介したような自覚症状があり、変形性膝関節症かもしれないと感じる方は、ぜひ一度イノルト整形外科までご相談ください。
イノルト整形外科では関節専門外来を設置しており、レントゲンはもちろんのことエコー検査やMRI検査(外部委託)などの高度な検査機器も用意し迅速かつ正確な診断が可能です。
また、上記でご紹介した体外衝撃波やハイドロリリース、再生医療といった最新の治療法にも対応しているため、初期から末期までさまざまな状態に合わせて最適な治療法をご提案させていただきます。
まとめ
膝の痛みはさまざまな原因によって現れることがありますが、中でも変形性膝関節症は代表的な疾患のひとつです。
初期段階では膝の違和感を覚える程度ですが、進行していくと徐々に痛みが強くなり、やがては歩行が困難になるほど重症化するおそれもあります。
日常生活に支障をきたさないようにするためにも、変形性膝関節症が疑われる症状が現れた場合にはできるだけ早めに治療をスタートさせることが大切です。
信頼性が高く多様な治療法に対応した整形外科クリニックをお探しの方は、ぜひ一度イノルト整形外科へご相談ください。
股関節の痛みの原因は?女性特有の痛みについても解説
慢性的な痛みに悩まされている方や、最近股関節に違和感を覚えるようになった方は、できるだけ早めに整形外科を受診することがおすすめです。
太ももから股関節のあたりに痛みを感じる場合、さまざまな疾患を発症しているサインの可能性があります。
特に、男性と女性を比較した場合、骨盤の形状やホルモンバランスなどが異なるため、女性のほうが股関節の痛みを発症するリスクは高い傾向もあります。
なぜ股関節に痛みが現れるのか、考えられる原因と疾患や治療法、痛みを改善するためのポイントなどを解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
股関節の構造
股関節は人間の身体で最も大きな関節の一つであり、下半身の運動や体重を支えるために重要な役割を果たしています。
股関節は、骨盤の寛骨臼と大腿骨の先端部分である大腿骨頭から形成されています。
寛骨臼はカップのような形をしており、球状の大腿骨頭を包み込むことで股関節の安定性とスムーズな動きを実現しています。
また、股関節は関節包と靭帯によっても保護されています。
関節包は関節を包む厚い膜で、関節液を分泌して関節の滑りを良くし、摩擦を減少させる役割を果たします。
靭帯は骨と骨を繋ぐ結合組織で、股関節の安定性を維持するために重要な役割を果たしています。
このように、ヒトの股関節はさまざまな骨や組織が複雑に絡み合いながら形成されているのです。
股関節の痛みの原因
股関節に痛みを感じる場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。
股関節自体の変形
加齢や遺伝、過度な運動によって負荷がかかりすぎると、変形性股関節症などの疾患を発症し股関節そのものの形状が変化することがあります。
変形の程度や部位によっては激しい痛みが生じるばかりではなく、正常な可動域が失われ日常生活にも支障をきたすことがあります。
軟骨の摩耗
関節の内部には軟骨が存在し、これがクッションのような役割を果たしています。
しかし、加齢や体重の増加、運動のしすぎなどによって軟骨が摩耗していくと、クッションの役割を果たすものがなくなり骨同士が直接接触するようになります。
その結果、激しい痛みが生じることがあります。
筋肉や腱の緊張や硬直
股関節の周りにある筋肉や腱は、関節を安定的に保つ役割を果たしています。
しかし、筋肉や腱が緊張し硬直してしまうと、柔軟性が失われ関節を安定的に固定できなくなり、痛みを引き起こすことがあります。
特に、筋肉の酷使や無理な姿勢、運動・ストレッチ不足などが原因となるケースが少なくありません。
関節唇の損傷
関節唇は股関節にある軟骨の一部で、股関節を安定させる役割を持っています。
特に、急な方向転換や激しい動きをするスポーツなどで日常的に股関節を酷使している方の場合、関節唇を損傷するケースが多く痛みや不安定感が生じることがあります。
関節包の炎症
関節包は関節液を保持し関節を滑らかに動かす役割を果たす組織です。
外傷や感染症、股関節の酷使などが原因で股関節に炎症が生じると、痛みの原因となることがあり、重症化すると股関節の可動域も狭くなる可能性もあります。
靭帯の伸びや損傷
股関節の周囲にある靭帯は関節を安定させる役割を果たしています。
激しい運動や事故・転倒などで股関節が不自然な方向に強く引っ張られると、靭帯が伸びたり損傷したりすることがあり、その結果股関節の不安定感や痛みが生じます。
関連記事:変形性膝関節症の治し方とは|痛いのに放っておくとどうなる?
股関節の痛みの原因となる病気・疾患
股関節の痛みを放置しておくと、重症化しさまざまな病気や疾患を発症するケースも少なくありません。
どういった疾患のリスクが高まるのか、一例をご紹介しましょう。
変形性股関節症
軟骨がすり減った状態になると股関節に激しい痛みが生じますが、これを放置しておくと変形性股関節症を発症する可能性があります。
変形性股関節症は骨同士が接触することで関節の形が変形し、強烈な痛みや関節の硬直、可動域の制限などが生じる疾患です。
主に加齢に伴う股関節の酷使や、急激な体重の増加、遺伝的要因などが原因となって発症します。
臼蓋形成不全
臼蓋形成不全とは、股関節の受け皿部分にあたる臼蓋が大腿骨頭を十分に覆いかぶさっていない状態を指します。
この状態では、大腿骨頭が骨盤にホールドされず不安定な状態になるため、股関節にかかる負担が増大します。その結果、変形性股関節症などの疾患を引き起こしやすくなります。
大腿骨頭壊死
大腿骨頭壊死とは、大腿骨の先端部分である大腿骨頭への血流が途絶え、骨組織そのものが壊死する疾患です。
主に外傷やアルコールの過剰摂取、ステロイド薬の長期服用などが主な原因として挙げられ、壊死が進行すると骨が崩壊し関節の変形と強烈な痛みを伴います。
先天性股関節脱臼
先天性股関節脱臼は、生まれつき股関節の形成異常があり、大腿骨頭が脱臼してしまっている状態です。
幼少期に適切な装具治療などを行なわずに放置してしまうと、骨盤まわりの正常な発育が妨げられ、その結果として変形性股関節症を発症し、強い痛みが発生することがあります。
グロインペイン症候群
グロインペイン症候群とは、股関節やその周辺の筋肉、腱、靭帯に現れる痛みや違和感などの総称であり、「鼠径部痛症候群」ともよばれます。
特にアスリートが発症するケースが多く、過度な運動や不適切なフォーム・動作による負荷の増大が主な原因となります。
梨状筋症候群
梨状筋症候群は、梨状筋という臀部にある筋肉が坐骨神経を圧迫し、痛みや痺れを引き起こす疾患です。
梨状筋が硬直すると、股関節や臀部、太ももに痛みが広がることがあります。
特にデスクワークで長時間同じ着座姿勢をとっていたり、股関節を無理に動かすことで症状が悪化します。
女性に多い股関節の痛みの原因
股関節の痛みは性別によってもその原因が異なる場合があります。
特に女性の場合、以下のような特有の原因が痛みを引き起こしていることが少なくありません。
臼蓋形成不全
女性に臼蓋形成不全が多い理由としては、男女の骨格の違いが挙げられます。
女性は男性に比べて骨盤が広いため、股関節の受け皿部分にあたる臼蓋が浅い傾向が見られます。
大腿骨頭の受け皿が浅いと臼蓋形成不全を起こしやすく、それに伴い痛みが現れることも少なくありません。
変形性股関節症
臼蓋形成不全が深刻化すると股関節への負担が増大し、変形性股関節症の発症リスクも高まります。
特に中高年の女性は、女性ホルモンの減少や体重増加などに伴い、変形性股関節症が深刻化しやすくなります。
ホルモンの影響
女性ホルモンの一種であるエストロゲンは、骨や関節の健康維持に重要な役割を果たしています。
しかし、閉経を迎えるとエストロゲンの分泌量が減少し、骨密度の低下や関節の軟骨がすり減りやすくなるなどの影響が出てきます。
その結果、股関節の痛みが発生するリスクが高まります。
股関節から膝にかけての痛みの原因
股関節だけでなく、それより下の太ももから膝のあたりにかけて痛みが現れるケースもあります。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。
変形性股関節症が膝の痛みを引き起こすことも
変形性股関節症によって股関節の可動域が制限されたり痛みを感じるようになると、膝関節が動きで痛みをカバーし強い負荷がかかります。
その結果、股関節から下の部位にかかる荷重のバランスが崩れ痛みの原因となることがあります。
最悪の場合、変形性膝関節症を発症し、股関節だけでなく膝関節の可動域が狭くなったり、関節の曲げ伸ばしができず歩行そのものが困難になる可能性もあります。
大腿四頭筋の問題
太ももを構成する外側広筋と中間広筋、内側広筋、大腿直筋の4つの筋肉を大腿四頭筋とよびます。
大腿四頭筋は太ももの曲げ伸ばしはもちろん、股関節の安定や曲げ伸ばしにも大きく寄与している筋肉です。
精密検査などの結果、股関節や膝関節そのものに異常が見られない場合には、大腿四頭筋が損傷していたり何らかの異常が発生している可能性もあるのです。
股関節が右だけあるいは左だけ痛くなるのはなぜ?
股関節の痛みは左右対称に現れることもあれば、右側あるいは左側のいずれかに偏って症状が現れるケースも少なくありません。
どちらか一方に症状が現れる原因は、ケガや外傷によって一方にのみダメージが加わることはもちろんですが、左右の股関節の発育に左右差が生じてしまった場合や、つねにどちらか一方に体重をかける癖がついていたり、椅子に座るときに脚を組む癖があるなど、日々の何気ない行動・動作も原因のひとつとして考えられます。
股関節の痛みの治し方
股関節の痛みを改善するためには、どのような治療法が有効なのでしょうか。代表的な治療法の例をいくつかご紹介します。
保存療法
保存療法とは、外科手術を行うことなく痛みの緩和や機能改善を目指す治療法です。
関節の痛みが感じられる場合には、まず保存療法が選択されるケースが非常に多く、もっとも基本的な治療法といえるでしょう。
具体的には痛み止めや湿布の処方、リハビリ、ハイドロリリース、体外衝撃波治療、再生医療などが保存療法にあたります。
再生医療
再生医療には、自己の脂肪などを利用した幹細胞治療や、自己の血液を使用したPRPや成長因子療法などがあります。
変形性股関節症や関節唇損傷に起こっている炎症を沈静化、一部修復してくれて、それ以上の悪化を防ぐため、手術を避けたい方にとってはとても良い選択肢です。
体外衝撃波治療
体外衝撃波という強力なエネルギー波を患部に当てることにより、即効性の鎮痛効果と損傷した組織の修復を行なってくれる治療器です。
泌尿器科の分野では体外衝撃波治療は尿路結石の破壊目的で治療として使われています。
ハイドロリリース
ハイドロリリースは筋性の痛みに対して、エコー検査で確認しながら生理食塩水などの体内に入れても大丈夫な水を注射し筋膜や神経の周囲を剥がすことにより滑走性を改善し痛みを解消しやすくなります。
理学療法士のリハビリ
リハビリも外科手術を行わない治療法ですが、主に股関節の筋力強化や柔軟性の向上、関節の安定性向上などを目的に行われます。
具体的にはストレッチや筋力トレーニングなどが代表的です。
股関節の痛みが比較的軽度で、疾患も深刻化していない場合には保存療法と物理療法を組み合わせた治療法が有効な選択肢となります。
手術療法
保存療法や物理療法で改善が見られない場合や、股関節の変形や損傷が進行している場合に検討されるのが手術療法です。
人工股関節置換術や寛骨臼回転骨切り術、股関節鏡視下手術などが代表的で、これにより股関節の機能を回復し、従来の痛みのない日常生活に戻れる可能性があります。
生活習慣の改善
さまざまな治療法によって股関節の痛みが改善された後も、症状を再発させないためには生活習慣を見直すことが大切です。
たとえば、体重の管理や適度な運動、正しい姿勢を保つことはもちろんですが、重いものを持ちながらの階段の昇降は避けるなど、股関節にかかる負担を減らす工夫も必要です。
股関節の痛みならイノルト整形外科まで!
股関節の痛みの原因はさまざまで、症状が現れている部位や痛みの程度が同じであったとしても根本的な原因や疾患は異なるケースがあります。
外傷とは異なり、目で見ただけで正確な状態や原因を判断することは難しいため、早めに整形外科を受診することが大切です。
イノルト整形外科では、股関節をはじめとしたさまざまな部位の痛みを治療する関節専門外来や、運動によって生じたケガに特化したスポーツ整形外科、最新の治療法として注目されている再生医療に特化した専門外来を設置しており、高度な知見をもった専門医が治療を担当します。
今回ご紹介した保存療法はもちろんのこと、手術療法も必要に応じて適切な医療機関に紹介が可能なため、症状が深刻化した患者様にも最適な治療法をご提案できます。
症状が深刻化し「治らないのではないか」と不安を抱いている方や、他院で治療を受けたものの症状が改善されなかったという方も、まずは一度イノルト整形外科までご相談ください。
関連記事:PRP(多血小板血漿)療法とは?効果や費用について解説
まとめ
股関節の痛みは関節自体の変形や損傷が原因となっているケースもあれば、軟骨の摩耗や筋肉の硬直、腱の損傷などさまざまな原因が考えられ、痛みを放置しておくと重篤な疾患につながる可能性もあります。
特に女性の場合は、骨盤の形状や女性ホルモンの影響などにより、男性に比べて股関節の痛みを発症しやすい傾向が見られます。
慢性的な痛みに悩まされている方や、最近股関節に違和感を覚えるようになった方は、できるだけ早めに整形外科を受診することがおすすめです。
脚の付け根が痛い!原因は何?おすすめのストレッチや注意点もご紹介

太ももから股関節にかけて、脚の付け根部分に痛みがあり、日常生活にさまざまな支障をきたしている方も少なくありません。
一口に痛みといっても症状の程度は異なり、脚の付け根の内側、外側、前側などの部位によっても考えられる原因や疾患はさまざまです。
そこで本記事では脚の付け根に痛みが現れる原因や代表的な疾患、痛みを緩和するための方法やストレッチの一例もご紹介します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
脚の付け根が痛い場合に考えられる原因とは

脚の付け根に痛みが感じられるのはどういった原因が考えられるのでしょうか。代表的な原因をいくつかご紹介します。
関節軟骨の摩耗
太ももと骨盤の接続部分である股関節の軟骨がすり減ると、炎症が起こることで痛みを引き起こすことがあります。
安静時には痛みが感じられなくても、脚を動かしたり立ち上がったときに痛みを感じることが多く、変形性股関節症を発症している可能性が高くなります。
股関節の不安定性
関節を支える筋肉が弱くなることで、股関節が不安定になり痛みを引き起こすことがあります。
極端な運動不足や先天性の問題によって引き起こされるケースが多く、ある決まった動作をしたときや体重をかけたときに関節の不安定感や痛みを生じさせます。
筋肉の硬直や緊張
大腿四頭筋や腸腰筋、内転筋といった股関節周辺の筋肉が硬直または緊張することで、筋肉に過度な負担がかかり痛みを生じさせることがあります。
初期の段階では脚を動かすときに違和感を覚える程度ですが、症状が悪化していくと激しい痛みや筋肉のこわばりなどが感じられるようになります。
腱の炎症
運動のしすぎや過度の負荷がかかることによって、股関節周辺の筋肉と骨をつなぐ腱が炎症し痛みを引き起こすことがあります。
特にアスリートや同じ動作を繰り返す現場作業員などの発症リスクが高く、安静時にはほとんど痛みが感じられないものの特定の動きをしたときに痛みを感じやすくなります。
関節包・滑液包の炎症
関節包とは、関節を保護している膜のような組織であり、その内部はクッションの役割を果たす滑液で満たされています。
感染症や外傷、免疫疾患などが原因で関節包が炎症を引き起こすことがあり、これによって激しい痛みを感じます。
股関節自体の変形
先天性による股関節の形状異常や、ケガの後遺症などが原因で股関節そのものが変形し、正常な動作が困難となり痛みを引き起こすこともあります。変形性股関節症の原因にもなりやすくなります。
関連記事:歩くと股関節が痛いときの原因は?股関節をほぐすストレッチを紹介
脚の付け根が痛い時に疑うべき病気・疾患

脚の付け根の痛みは、部位によって疑うべき病気や疾患が異なります。
外側が痛い場合
脚の付け根の外側に痛みを感じる場合には、主に関節の歪みや筋力の低下などによって身体のバランスが崩れていることが考えられます。
考えられる疾患としては以下の通りです。
- 変形性股関節症
- 股関節臼蓋形成不全
- 大腿骨近位部骨折 など
運動不足などによって体重が急激に増加すると筋力で体重を支えきれなくなり、関節に大きな負担がかかり症状を悪化させることが少なくありません。
内側が痛い場合
内側に痛みを感じる場合には、急な動きや過度の運動、筋肉の疲労などによって関節・腱に炎症が起こり痛みとなる可能性が考えられます。
- 坐骨神経痛
- グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群) など
上記のうち、坐骨神経痛は治療をせず放置しておくと椎間板ヘルニアなどの疾患につながるリスクもあります。
前側が痛い場合
前側に痛みを感じる場合には、主に股関節の変形や歪みなどが原因として考えられ、特に長時間のデスクワークを行っている人ほどリスクが高まります。
- 鼠径ヘルニア
- 股関節唇損傷 など
上記のうち、鼠径ヘルニアは関節の痛みだけでなく、脚の付け根の部分に小さな盛り上がり(しこり)が現れることも少なくありません。
股関節が右だけあるいは左だけ痛む原因は?
股関節の痛みは左右対照的に症状が現れることもあれば、どちらか一方のみに症状が現れることもあります。
左右いずれかのみに痛みが現れるのはどういった原因が考えられるのでしょうか。
片側への過剰な負担
日常生活やスポーツにおいて、一方の脚に過度の負担がかかることが1つ目の原因として考えられます。
片足に重心をかける姿勢が癖になっていると、一方の股関節に過度のストレスがかかり炎症や痛みを引き起こしやすくなります。
関節臼の形成不全
先天的に股関節の関節臼が正常に形成されていない場合、股関節が不安定になりやすく片側の関節に過度の負荷がかかることがあります。
その結果、軟骨がすり減ったり、炎症や痛みを引き起こすことがあります。
左右で脚の長さが違う
生まれつき、あるいは外傷や手術の後遺症などにより、脚の長さが左右で異なるケースがあります。
このような場合、長い方の脚に体重の負荷が集中し股関節に痛みを生じさせることがあります。
坐骨神経痛
長時間のデスクワークや運動などによって坐骨神経が圧迫されると、坐骨神経痛を発症し片側の臀部から脚の付け根にかけて痛みが生じることがあります。
坐骨神経痛は片側のみに症状が現れることが多く、股関節から太ももにかけて鋭い痛みやしびれを引き起こします。
ケガ・損傷
スポーツや事故、転倒などが原因で股関節の周囲の筋肉、腱が損傷すると、片側にのみ痛みが生じることがあります。
関連記事:変形性股関節症の治し方はある?やってはいけないことや負担をかけない寝方を紹介
脚の付け根が急に痛くなった時の治し方
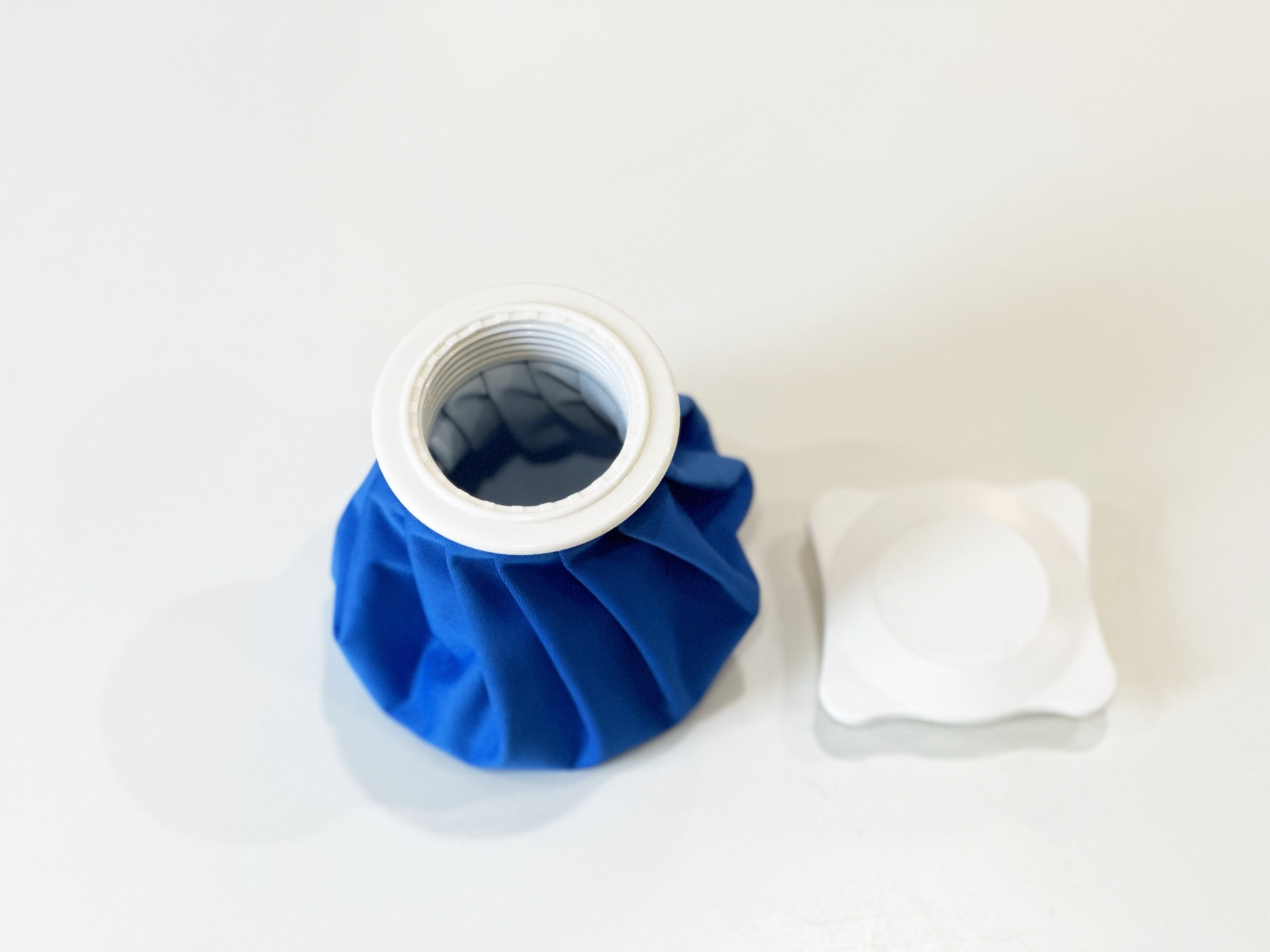
脚の付け根に痛みを感じる場合、誤った対処をしてしまうと症状を悪化させる可能性もあります。
早期に症状を緩和するために、正しい対処法を覚えておきましょう。
安静にする
痛みが生じた場合は運動を控え、痛みのある脚を安静に保つことが大切です。
無理に動かすことで痛みが悪化する可能性があるため、痛みが和らぐまでは脚を休めておきましょう。
冷やす
事故やスポーツによってケガをして急な痛みが生じた場合は、患部を冷やすことも大切です。
氷嚢を痛みのある箇所に当て患部を冷却することで、血管が収縮し腫れや炎症を抑え重症化を防げる可能性があります。
痛み止めの使用
激しい痛みが感じられる場合、市販の痛み止めを服用することで一時的に痛みを抑えることができます。
ただし、痛みを感じないからといって無理に身体を動かすと症状を悪化させる危険もあるため、あくまでも安静を心がけましょう。
ストレッチや軽い運動
痛みがある程度引いてきたら、ストレッチや軽い運動を行うことで筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高めることができます。
この場合も無理は禁物で、痛みを感じるようであれば無理に動かさず徐々に可動域や負荷を上げていくことが大切です。
整形外科の受診
数日経っても痛みが改善しない場合や、腫れが悪化しているような場合には速やかに整形外科を受診しましょう。
専門医による診断を受けることで、正確な原因を特定し適切な治療を受けることができます。
また、ストレッチや軽い運動を行う場合、症状を悪化させないためにも専門の理学療法士のアドバイスや指導を受けることが理想的です。
脚の付け根の痛みに効果的なストレッチと注意点
脚の付け根を改善するために、自宅でできるストレッチや軽い運動をご紹介しましょう。
効果的なストレッチ

- 仰向けに寝た状態で左右の膝を90度程度曲げる
- 両手を腰の下に入れる
- 左脚を外側に倒し、もとの位置に戻す
- 3を10回程度繰り返す
- 右脚も同様の動作を行う
1の膝を曲げる際には、左右の足をくっつけることを意識しましょう。
また、3の脚を外側に倒す際には、片方の膝は立てた状態をキープすることと、かかとからつま先もできるだけ片方の足にくっつけた状態で膝を倒すことが大切です。
注意すべきストレッチ

一見すると股関節に効きそうなストレッチも、実は痛みがあるときには避けたほうが良い場合があります。
特に注意すべきなのが、上半身と下半身を捻ったり大きく反らしたりするストレッチです。
ヨガなどで多く見かけるポーズですが、これらは股関節に大きな負荷がかかることから、炎症や痛みがある状態で無理な姿勢をとってしまうと症状を悪化させるリスクがあります。
脚の付け根が痛い場合はイノルト整形外科まで
脚の付け根の痛みはさまざまな原因が考えられ、それに対応した適切な治療を行わなければなりません。
慢性的な痛みを放置しておくと関節そのものが変形し、日常生活にもさまざまな支障をきたす可能性も考えられるため、できるだけ早めに整形外科を受診することがおすすめです。
イノルト整形外科では、股関節をはじめとしたさまざまな部位の痛みを治療できる関節専門外来や、スポーツを起因としたケガや不調に対応できるスポーツ整形外科、さらには最新の治療法である再生医療を専門とした外来も設置しています。
専門医による丁寧なカウンセリングと検査を実施し、患者様に適した治療プランを提示させていただきます。
一般的な整形外科では対応が難しい再生医療や体外衝撃波治療、ハイドロリリース治療などにも対応しているため、「他院で診療を受けたものの期待通りの効果が得られなかった」という方もぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
脚の付け根に痛みがある場合、股関節の疾患や筋肉、腱の炎症などさまざまな原因が考えられ、それぞれに対応した治療を行わなくてはなりません。
痛みがある程度引いてきたらストレッチを行ってみるのもひとつの手ではありますが、正しい方法を理解していないと症状を悪化させるリスクもあります。
そのため、脚の付け根の痛みを早期に治療するためには信頼性の高い整形外科を受診することが何よりも大切です。
イノルト整形外科ではリハビリテーションや保存療法といった基本的な治療法はもちろんのこと、体外衝撃波やハイドロリリース、再生医療といった最新の治療法も選択でき、患者様の状態に合わせて最適な治療法をご提案しています。
慢性的な痛みに悩まされている、他院で治療しているものの期待通りの効果が得られないという方は、ぜひ一度イノルト整形外科へご相談ください。
膝の皿の上が痛い原因とは?突然の痛みや、疾患や治し方について解説
膝の皿の上に痛みを感じる場合、さまざまな疾患が考えられます。
なぜ痛みが発症するのか、その原因を解説するとともに、痛みを感じた時に自分自身でできるセルフケアの方法、医療機関で受けられる主な治療法、治し方などを解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
膝の皿の上が痛い場合に考えられる原因・疾患とは?
膝の皿の上に痛みがある場合、どのような疾患が考えられるのでしょうか。また、その原因として考えられる点もあわせて解説します。
大腿四頭筋腱炎
大腿四頭筋は大腿に位置する4つの筋肉群であり、膝の曲げ伸ばしをサポートする重要な役割を果たしています。
これらの筋肉は骨盤から膝にわたって伸びていますが、膝の頻繁な曲げ伸ばしや日常的な酷使、過度の負荷がかかることで筋肉の接続部分である腱に炎症が生じることがあります。
特にスポーツ選手が発症するケースが多く、主な症状としては膝の上部に痛みや腫れが現れます。
膝蓋腱炎(ジャンパー膝)
膝蓋腱は膝蓋骨(膝の皿)と脛骨をつなぐ腱であり、歩行やジャンプ、膝の屈伸運動に欠かせない組織のひとつです。
膝蓋腱炎とは膝蓋腱に炎症が起こる疾患で、別名「ジャンパー膝」とよばれることもあります。
その名の通り、バスケットボールやバレーボールなど頻繁にジャンプを繰り返すスポーツで発生しやすく、膝の前部に鋭い痛みが生じることが特徴です。
膝蓋大腿関節の変形性関節症
膝蓋大腿関節における変形性関節症とは、膝蓋骨と大腿骨の接触部分である関節内部の軟骨が摩耗し、痛みや硬直といった症状を引き起こす疾患です。
加齢や急激な体重の増加、膝の酷使、関節への過度な負荷などが原因で発症することが多く、症状が悪化すると関節そのものが変形することもあります。
膝蓋下脂肪体炎
膝蓋下脂肪体は膝蓋骨のそばに位置する脂肪組織であり、膝関節の動きを滑らかにする役割を果たしています。
膝への負荷がかかりすぎると膝蓋下脂肪体に炎症を引き起こすケースがあり、膝の皿の上のあたりに痛みや腫れが現れます。
膝蓋前滑液包炎
膝蓋前滑液包とは、膝蓋骨の上部に位置する小さな液体で満たされた袋状の組織で、関節の摩擦を低減する役割を果たしています。
膝蓋上滑液包炎は膝蓋前滑液包が炎症を起こす疾患であり、いわゆる「膝に水が溜まった状態」のことです。
初期症状としては膝の圧迫感や違和感、軽い痛みなどが現れますが、症状が進行していくと膝の上部に激しい痛みや腫れ、熱感などが生じることもあります。
こちらも膝の酷使や大きな負荷、あるいは外傷などが原因となることが多く、膝の曲げ伸ばしを繰り返していくうちに徐々に痛みが悪化しやすくなります。
関節リウマチ
関節リウマチとは、免疫の異常が原因で体のさまざまな関節に痛みや腫れなどが現れる疾患です。
本来、免疫は細菌やウイルスから守り私たちの健康を維持する役割を果たしていますが、何らかの異常によって免疫機能が正常に機能しなくなり、関節の一部を攻撃・破壊してしまうことで関節リウマチは発症します。
関節リウマチは一般的に30〜50代の女性が発症するケースが多いですが、明確な原因は分かっていません。
関連記事:膝に水が溜まるとはどういう状態?原因や症状について解説
膝の皿の上が痛い時の対処法
膝の皿の上に痛みがあるとき、セルフケアを行うことで一時的に症状を緩和できる可能性があります。
状況に合わせた適切なセルフケアの方法を解説しましょう。
安静と活動の制限
スポーツや仕事など膝の酷使によって膝の痛みが現れた場合には、一時的に活動を制限し安静を心がけましょう。
無理に膝を動かすと症状を悪化させ、歩行が困難になったり長期の治療を要する可能性もあります。
アイシング
スポーツは怪我によって膝に無理な力が加わって強烈な痛みが生じたり、熱感や腫れなどが現れた場合には患部を氷嚢などでアイシングしましょう。
コールドスプレーや絞ったタオルなどは冷却効果が限られるため、氷または保冷剤によるアイシングが効果的です。
サポーターやテーピングによる圧迫と固定
患部の痛みが持続し症状が緩和されないときには、サポーターやテーピングによって患部を固定することが有効です。
膝の関節を固定することでそれ以上の症状悪化を防ぎ、日常生活における動作も楽になります。
痛みが出ない範囲でのストレッチ
適切な方法でストレッチを行うことも痛みの緩和に役立つことがあります。
本来ストレッチは理学療法士の指導のもとで行うのが理想的ですが、通院まで時間がかかる場合などは痛みを感じない程度の範囲でストレッチを行うのがおすすめです。
膝のストレッチでは、深い屈伸や曲げ伸ばしを行うと痛みを悪化させる危険もあるため、くれぐれも無理をしないよう心がけましょう。
クッション性のあるソールの使用
ジャンプやランニングなどの際に痛みがある場合には、靴やソールを見直すことで緩和できる可能性があります。
適度な厚みがありクッション性に優れたソールがおすすめです。
膝の皿の上が痛い時の治し方
上記でご紹介した内容はあくまでも一時的に症状を緩和する方法に過ぎません。痛みの原因を根本から解消するためには医療機関での治療が必要です。
理学療法士のリハビリテーション
痛みの根本原因を解消し再発を防止するためには、膝関節周辺の筋力をアップしたり、柔軟性や姿勢を改善したりすることで、痛みのなかった頃の状態を取り戻す必要があります。
そこで最も重要な治療法となるのが理学療法士の指導のもとで行われるリハビリテーションです。
専門的な知識をもった理学療法士が指導を行うことで痛みが再発することを予防しやすくなります。
物理療法
物理療法とは、レーザーや温熱、電気といったさまざまなエネルギーを患部に照射し、物理的刺激を与えることで痛みを低減する治療法です。
膝関節の物理療法としては以下の治療法が代表的です。
対して、一部の整形外科で数十年前から行われているマイクロ波やホットパックは治療効果はないと言われており、これらを未だに行っている整形外科は要注意です。
体外衝撃波(集束・拡散)
体外衝撃波とは、高エネルギーの衝撃波を患部に照射することで、炎症を起こした損傷した組織の再生を促す治療法です。
ピンポイントの照射を行う収束型と広範囲の照射が可能な拡散型があります。
整形外科においては比較的新しい治療法であり、対応可能なクリニックも限られています。
超音波・低周波治療
体外衝撃波と比べると治療効果は比較的小さくなりますが、物理療法の中で一般的なのが、超音波や低周波を用いた治療法です。
超音波治療では体内の組織を振動させることで、痛みの緩和や損傷した組織の自己治癒を促進する働きが期待できます。
一方、低周波治療は広範囲にわたる痛みを緩和する効果などが得られます。
いずれも、マイクロ波やホットパックなどの物理療法治療器と比べると疼痛に対する効果は得られやすくなっています。
再生医療
再生医療とは、自己の未熟な細胞を培養したり、血液から一部成分を取り出し、それを体内に膝関節などに注射することで損傷した部位の再生や痛みの改善を促す治療法です。
整形外科の分野において新たな治療法として注目されています。
幹細胞治療
ヒトの体内には神経細胞や筋肉細胞などさまざまな細胞に分化できる幹細胞があります。
脂肪などから採取・培養した幹細胞を患部に注入し、損傷した組織の再生を図るのが幹細胞治療とよばれる方法です。
成長因子療法
PRPの血小板などの細胞成分を除去して成長因子だけを集めたものを患部に注射する成長因子療法も増えてきています。
これを患部に注入することで炎症の治癒や痛みの軽減、関節の機能改善などにつながります。
PRP療法・成長因子療法
患者様本人の血液から多血小板血漿(PRP)とよばれる成分を抽出し、患部に注入する治療法です。
PRPには組織の修復を促進する成長因子を生成する働きがあり、これにより損傷した膝関節の機能を取り戻せる可能性があります。
幹細胞上清液
幹細胞の培養過程において生じる上清液には組織の修復を促進する成長因子が多量に含まれています。
これらの成長因子が働いてくれることで、幹細胞治療に近い効果が期待できます。
こちらは前述の3つとは異なり、他人の胎盤や抜けた歯から取り出した幹細胞が作り出しているもので、他人の細胞を使った治療になります。
ハイドロリリース
ハイドロリリースは筋膜リリース注射ともよばれ、癒着した筋膜に生理食塩水などを注射し患部の痛みを改善する治療法です。
膝の靭帯が伸びにくくなっている場合などに、ハイドロリリースを行うことで動きが改善されることがあります。
動注療法
動注療法とは、「モヤモヤ血管」とよばれる疾患を改善するために行われることの多い治療法です。
モヤモヤ血管とは痛みの原因となる異常な血管のことで、正常な血管とは異なり細くいびつな構造をしているのが特徴です。
モヤモヤ血管の治療にあたっては、体に入れても問題のない抗生物質をそのモヤモヤ血管に注入して詰まらせることで、痛みが緩和されやすくなります。
薬物療法
一時的な膝の痛みや初期段階の疾患など、短期間の痛みや炎症を取り除くために、痛み止めの内服薬や湿布、軟膏などが処方されることが多くあります。
関連記事:関節リウマチの症状は膝に出ることもある?変形性膝関節症との違いとは
イノルト整形外科での膝の痛みに対する治療
一口に膝関節の痛みといってもその症状や程度はさまざまであり、根本から改善するためには医療機関での検査と専門的な治療が不可欠です。
しかし、整形外科クリニックによっても対応できる治療法は限られているほか、信頼できる医療機関を探すのは簡単なことではありません。
膝の痛みを早期に改善し本来の機能を取り戻したいとお考えの方は、イノルト整形外科へご相談ください。
イノルト整形外科では関節専門外来を設置しており、膝はもちろん肩や肘、股関節、手足などさまざまな部位の痛みに特化した診察を行っています。
今回ご紹介した体外衝撃波やハイドロリリース、さらには再生医療といった最新の治療法にも対応しているため、症状や疾患の程度を考慮しながら最適な治療法を選択できます。
今回紹介した治療法は一部を除き自費診療となるため、対応している整形外科クリニックはごく少数に限られていますが、イノルト整形外科では膝に特化して診察が可能な専門外来を設置しております。
関連記事:膝の痛みの場所別原因まとめ|突然ズキズキ痛むのは危険?
まとめ
膝の皿の上が痛い場合には、主に大腿四頭筋腱炎や膝蓋腱炎などの疾患が考えられますが、それ以外にも変形性膝関節性や膝蓋前滑液包炎、関節リウマチなどを発症している可能性もあります。
主にスポーツや体重増加、日常的な膝の酷使などが原因で痛みが現れることが多く、重症化する前に医師の診察と治療を受けることが大切です。
ハイドロリリースや再生医療といった最新の治療法も含めて検討したいという方や、信頼できる整形外科クリニックをお探しの方はイノルト整形外科へお気軽にご相談ください。