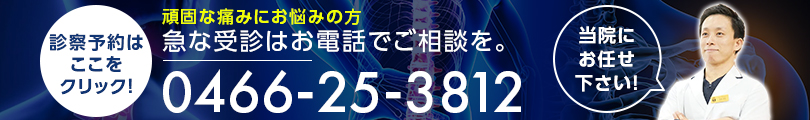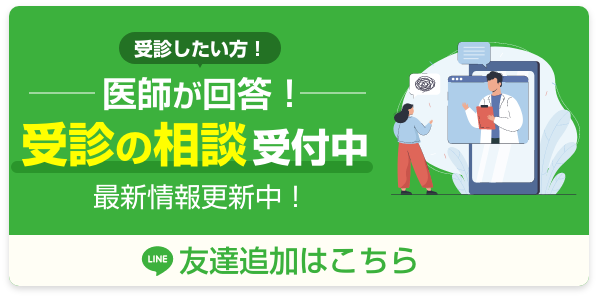股関節が痛いのは何が原因?痛い時にやってはいけないこととは

股関節周辺はデリケートな部位であることから、痛みや違和感などがあっても他人に相談しにくいものです。
しかし、長期間にわたって放置しておくと症状が進行していき、日常生活にも支障をきたすケースがあります。
股関節の痛みは何が原因となって引き起こされるのか、疾患の種類や痛みを緩和するためのケアなどを中心にご紹介します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
股関節が痛いときに考えられる原因・疾患とは?

股関節に痛みを伴う疾患にはさまざまなものがあります。考えられる疾患と、何が原因で痛みを引き起こすのかを詳しく解説しましょう。
股関節唇損傷
股関節唇損傷とは、大腿骨の付け根と骨盤を取り囲む股関節唇(こかんせつしん)という軟骨組織が損傷し痛みを引き起こす疾患です。
股関節唇は股関節の安定性を保つ役割を果たしていますが、多くは加齢に伴いもろくなり、日常生活できっかけなく痛めてしまうケースが多いです。
それ以外には、股関節を横に深く曲げるスポーツなどをよくする方もしばしば起こります。
股関節周囲の痛み以外にも、不安定感やカクつき感などが見られることもあります。
治療をせず放置しておくと悪化し、変形性股関節症などにつながるケースも少なくありません。
変形性股関節症
変形性股関節症とは、股関節の軟骨が摩耗し関節の形状そのものが変化する疾患です。
生まれつき臼蓋形成不全といって股関節の骨盤側の屋根が小さいために、股関節唇が損傷しやすくなり、さらに加齢に伴って発症するケースが多いです。
それ以外にも肥満や過度の負荷、運動不足などによって引き起こされるケースがあります。
股関節周囲の痛み以外にも、腫れやこわばり、歩行時の違和感なども症状として現れます。
すり減りが進行していくと、痛みが悪化し、最終的には人工関節置換術という手術が必要になります。
鼠径部痛症候群
鼠径部痛症候群はグロインペイン症候群とも呼ばれ、太ももの付け根部分にあたる鼠径部や下腹部などに痛みを生じる疾患です。
安静時や日常動作には支障がないものの、スポーツなど激しい運動や特定の動作を行った際に痛みが現れることが多くあります。
特にスポーツによってケガをした際、治りきっていないのに無理にトレーニングをしたり、骨盤に無理な力が加わることで発症することが多いとされています。
股関節の問題、筋肉や腱の損傷、神経の圧迫、内臓の疾患などが関与することがあります。
大腿骨頭壊死
大腿骨頭壊死とは、骨盤との接続部分である大腿骨の頭部に血流が不足することで、骨組織が壊死する疾患です。
股関節の強烈な痛みのほか、腰痛や歩行時の不安定感などが主な症状として現れますが、人によっては痛みを感じないまま進行するケースもあります。
重症化すると、股関節が変形していき、人工股関節置換術の手術が必要になる場合もあります。
大腿骨壊死の発症原因は明確に分かっていませんが、アルコールの摂取やステロイドの使用などが一因として考えられています。
大腿骨近位部骨折(頚部・転子部骨折)
大腿骨近位部骨折とは、大腿骨の付け根の部分が折れる疾患です。
主に高齢者や重度の骨粗鬆症患者が転倒することにより発症することがほとんどで、激痛により自力で立ち上がることすらできなくなります。
ほとんどの場合が、救急搬送されて緊急入院から手術を余儀なくされます。
ペルテス病に
ペルテス病は、主に成長期の子どもに見られる大腿骨の成長障害で、大腿骨の付け根部分が血流不全によって壊死し、股関節の痛みや不快感を引き起こします。
痛みは股関節から腰部、膝関節にまで広がり、歩行時に悪化することがあります。
ペルテス病の発症原因は明確に分かっていませんが、外傷や一時的な炎症が悪化した結果発症に至るケースもあるようです。
単純性股関節炎
単純性股関節炎も、10歳以下の子どもに多く発症する疾患です。
股関節や太ももに痛みが生じるほか、関節の可動域も制限されるため片足を引きずって歩いたりする症状が見られます。
短期間で自然と軽快するのであまり心配はいりません。
年齢別|股関節痛の特徴と対策

一口に股関節痛といってもさまざまな疾患が考えられ、年齢によっても傾向が異なります。
成人での股関節痛
社会人もしくは中高年世代の方で股関節に痛みがある場合には、股関節唇損傷や変形性股関節症、大腿骨壊死、大腿骨近位部骨折などさまざまな疾患が考えられます。
特に、股関節唇損傷は将来的な変形性股関節症にも繋がりやすく、レントゲンには異常として映らず、最初は見逃されやすいものです。
少しでも痛みや違和感がある場合には早めに整形外科を受診しましょう。
中学生、高校生での股関節痛
中学生や高校生の場合は、体育の授業や部活、スポーツクラブなどで体を動かす機会が多いことから、鼠径部痛症候群に悩まされるケースが少なくありません。
特に長距離のランニングやサッカーなどで蹴り上げる動作を行う場合、下腹部や骨盤のあたりに無理な力が加わり股関節の痛みを発症することがあります。
股関節に痛みや違和感を感じた場合には、無理に運動を続けることは厳禁です。
また、予防のためにもウォームアップのストレッチやマッサージが重要です。
痛みが長時間続く場合には、早めに整形外科を受診してください。特にスポーツ整形外科をうたっているクリニックが理想的です。
小児の股関節痛
小学生や幼児が発症する股関節痛は、ペルテス病や単純性股関節炎に起因しているケースが多くあります。
特にペルテス病は男児に発症する傾向が高く、股関節から腰、膝のあたりまで広範囲に痛みが現れることもあり見逃されやすいので要注意です。
痛みを訴えたり不自然な歩き方が見られる場合には、早めに小児に詳しい整形外科を受診し治療を行いましょう。
関連記事:股関節が外れるような感覚やずれる原因は?|直し方や治療法を解説
股関節が痛いときに自宅でできるセルフケア

股関節に痛みがあるものの、時間帯やタイミングによってはすぐに整形外科を受診できないケースもあるでしょう。
そのような場合に、自宅で簡単にできるセルフケアをご紹介します。
トリガーポイント(ツボ)押し
一時的に痛みを緩和したい場合には、股関節に効くツボ押しがおすすめです。
骨盤周辺には多くのトリガーポイントが集中しているため、横向きに寝た状態で骨盤に沿って心地良いと感じる部分を押してみましょう。
代表的なツボとして、骨盤の外側、Vラインと腰の際のあたりがあります。
股関節の痛みに効くストレッチ
以下のようなストレッチを行い、股関節周辺の筋肉をほぐすことで痛みを軽減できる場合もあります。
- 椅子に座り左右いずれかの足を曲げて片方の太ももの上に乗せる
- 上半身をゆっくり前方に倒し20秒ほど静止する
- 左右の足を入れ替えて1〜2を行う
股関節を温める、適度に身体を動かす
血行不良や筋肉の緊張などが原因で痛みを発症している場合には、関節を温めることで緩和できることもあります。
ぬるめのお湯を浴槽に張り、じっくりと温めることで血行が緩和され痛みも低減されます。
また、上記で紹介したストレッチや軽めのウォーキング、筋力トレーニングなどを行い体を動かすことで、股関節の柔軟性が高まり痛みが緩和できるケースもあります。
ただし、いきなりハードな運動は避け、強い痛みを感じたら無理をせず安静にすることも大切です。
股関節の右/左だけ痛いときの治し方
股関節の痛みは左右対称に現れるケースもあれば、左右のいずれかに痛みが現れるケースも少なくありません。
特に、上記で紹介した変形性股関節症や股関節唇損傷などの疾患にかかっている場合、片方にだけ痛みが現れるケースは珍しくありません。
トリガーポイントやストレッチ、マッサージなどで一時的に痛みを和らげることはできるかもしれません。
しかし、これらは根本的な解決にはならないため、早めに整形外科を受診することが大切です。
関連記事:変形性股関節症の治し方はある?やってはいけないことや負担をかけない寝方を紹介
股関節が痛い時にやってはいけないことは?
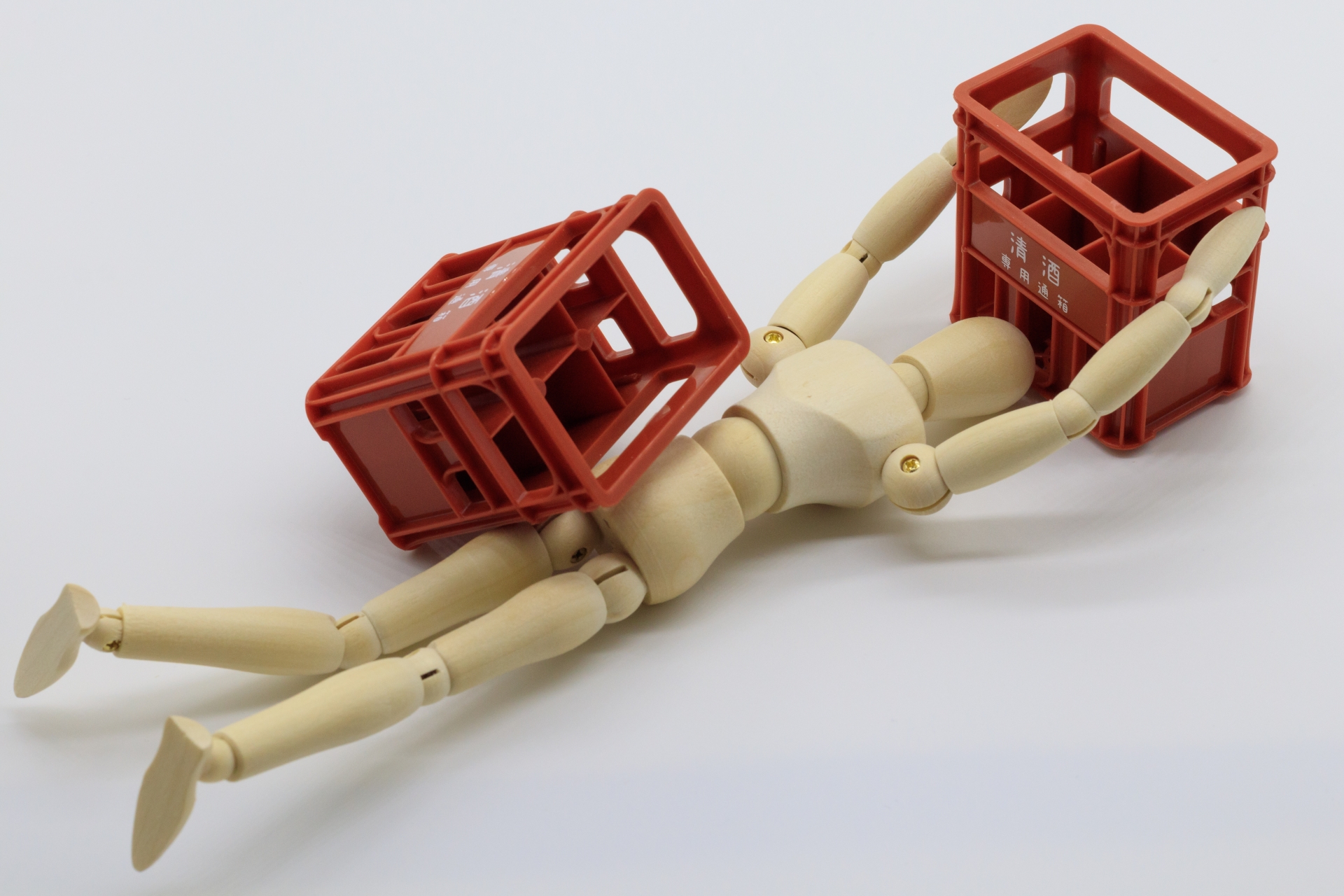
股関節に痛みがあるとき、必要以上に負担をかけてしまうと症状を悪化させることがあります。特に、以下の動作は避けるようにしましょう。
重い物を持ち上げる
重い物を持ち上げる動作は、腰や股関節に大きなストレスをかけることになります。
特に股関節に痛みがある場合には、無理に負担をかけないようにすることが重要です。
激しい運動
激しい運動や高負荷の運動も避けるべきです。
特にジョギングやバスケットボールなどは股関節に大きな負担をかけるため、痛みを悪化させる可能性があります。
股関節の痛みを和らげるためには、軽めのウォーキングや筋力トレーニング、水泳(平泳ぎ以外)など、低負荷の運動がおすすめです。
急な動作
急な動作や方向転換は、瞬間的に大きな負荷をかけることがあります。股関節が痛い場合、急な動作を控えることで痛みを軽減できます。
たとえば、階段の上り下りや急な坂道を上る際は、ゆっくりとした動きを心がけることが重要です。
誤ったストレッチ方法
股関節の痛みを和らげるためにストレッチを行うことは有効ですが、誤ったストレッチ方法を使うと逆に痛みを悪化させる可能性があります。
ストレッチを行う際は、痛みを感じない心地良いと感じる範囲で行うことが大切です。
また、理学療法士や作業療法士などの指導を受けることで、安全かつ効果的なストレッチ方法を学ぶことができます。
関連記事:股関節の左や右だけが痛むのはなぜ?痛みがおこる場所と原因を解説
股関節の痛みのご相談ならイノルト整形外科痛みと骨粗鬆症クリニックまで
股関節に痛みを発症する原因はさまざまで、中には深刻な疾患を発症しているケースも少なくありません。
治療を受けず放置していたり、誤った認識のままストレッチや運動を行うと、症状が悪化し重篤な状態に陥る可能性もあるでしょう。
痛みの程度や感じ方、症状が現れている部位だけで判断することは難しいため、できるだけ早めに専門のクリニックを受診することが大切です。
イノルト整形外科痛みと骨粗鬆症クリニックでは、関節専門外来を設置しており、股関節の痛みやさまざまな疾患の治療に対応できます。
また、理学療法士によるリハビリ、ストレッチの指導を受けたり、症状が進行している場合には外科手術による治療も受けられます。
股関節の痛みを早期に緩和したい方は、ぜひ一度イノルト整形外科痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください。
まとめ
股関節の痛みは股関節唇損傷や変形性股関節症、鼠径部痛症候群などさまざまな疾患が考えられます。
治療をしないまま放置しておくと関節が変形し本来の機能を果たせなくなる可能性もあります。
トリガーポイントやストレッチ、マッサージなどで痛みを一時的に緩和することは可能ですが、根本的な解決にはなりません。
症状が重篤化する前に、早めに整形外科を受診し治療に取り掛かりましょう。
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックのアクセスマップ
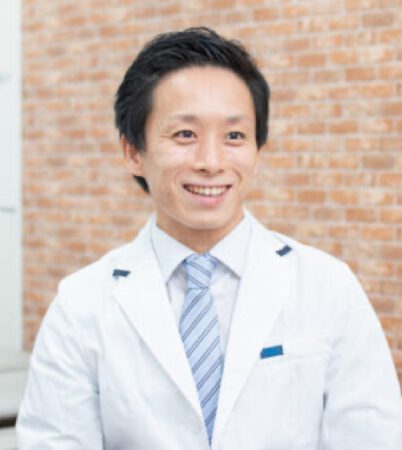
藤沢駅前 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長 渡邉 順哉
経歴
●東邦大学 医学部 卒業
●横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
●イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長