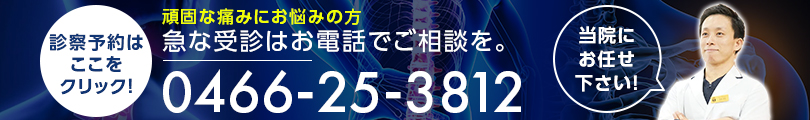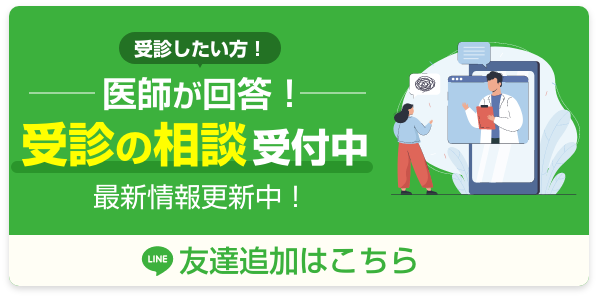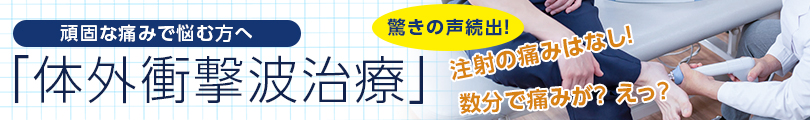関節リウマチの症状は膝に出ることもある?変形性膝関節症との違いとは

30代から50代頃にかけて発症することの多い関節リウマチは、体の節々に炎症が生じ、痛みや腫れなどを引き起こす疾患です。
発症する部位は人によってもさまざまです。
関節リウマチの好発部位は手や指の関節ですが、実は膝関節のような大きな部位に現れるケースがあることをご存知でしょうか。
本記事では、関節リウマチによる膝関節症の主な症状や変形性膝関節症との違い、治療法や対処法などを詳しく解説します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
関節リウマチによる膝関節症とは?
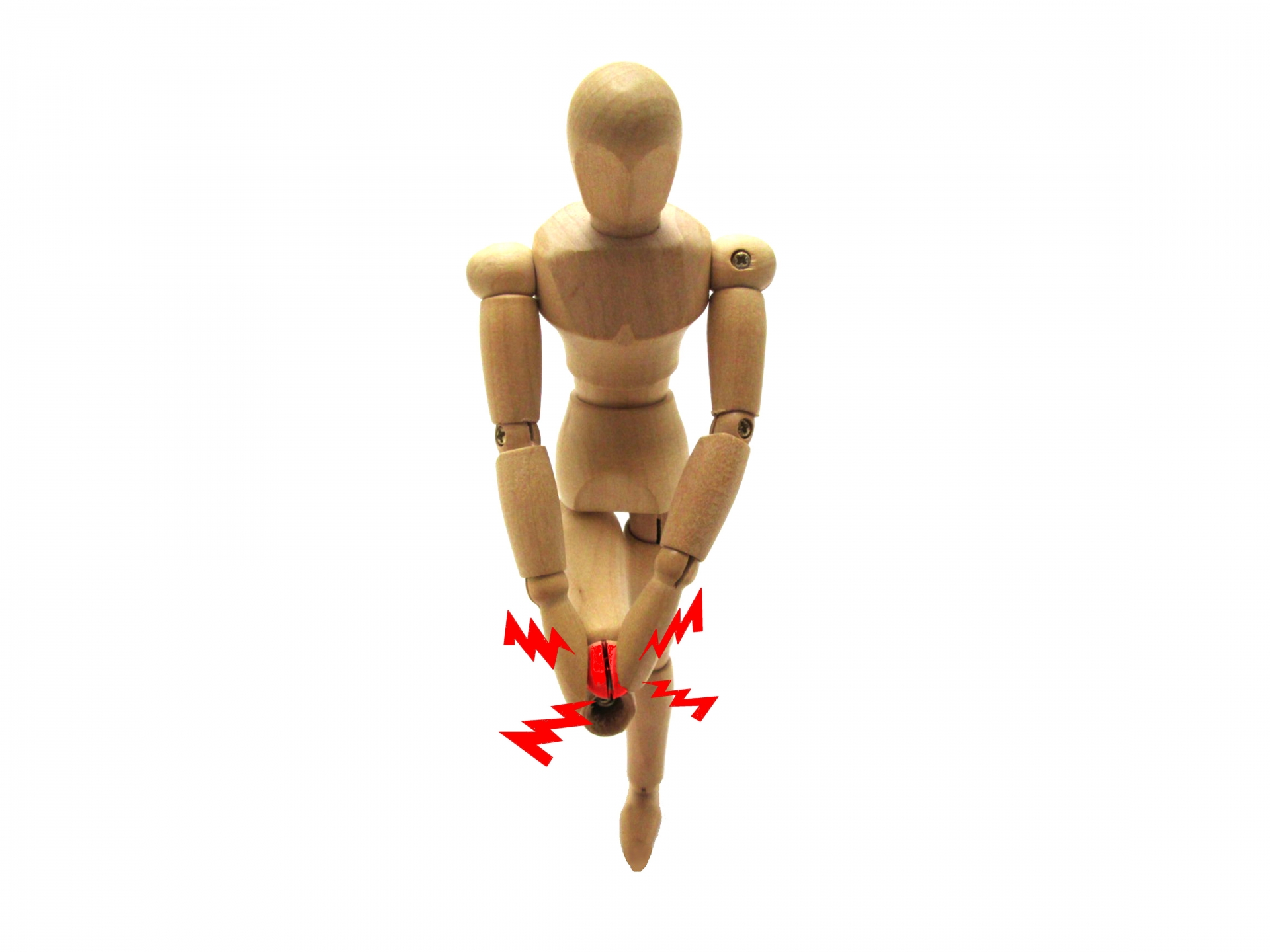
関節リウマチとは免疫疾患の一種であり、正常であるはずの体の関節を免疫細胞が攻撃し炎症を引き起こす疾患です。
関節リウマチを発症すると、関節内部にある滑膜とよばれる組織が攻撃され、関節液が過剰に分泌されます。
本来、関節液は関節の動きをスムーズにする役割を果たしているのですが、関節リウマチによって過剰に分泌されると神経を圧迫し、腫れや痛みなどの症状を引き起こします。
やがて重症化すると、滑膜が異常に増殖し、膝関節の軟骨や骨、靱帯など関節の構造を破壊し、関節機能を損なうケースも少なくありません。
関節リウマチ以外にも膝の痛みや腫れを引き起こす疾患は多く、特に「変形性膝関節症」が有名です。
関節リウマチと変形性膝関節症の症状は似ていますが、違いがあります。
関節リウマチは、膝に限らず体のさまざまな関節部位に症状が現れるのに対し、変形性膝関節症は膝関節のみなど一部だけに現れることが多いです。
また、関節リウマチは関節の痛みだけでなく、微熱や貧血、全身の倦怠感といった症状も現れることが多くあります。
関節リウマチが疑われた場合、採血検査や関節エコー検査により編家姓膝関節症と鑑別することが可能であり、速やかに関節リウマチの治療に移行することが出来ます。
関連記事:関節リウマチの原因はストレス?なりやすい性格がある?
関節リウマチによる膝関節症の症状
関節リウマチは体のさまざまな部位に症状が現れますが、膝関節に現れる症状はどういったものなのでしょうか。代表的な症状を3つご紹介します。
膝の痛みと腫れ
関節リウマチによって膝関節に炎症が続くと、関節液が過剰に分泌され圧迫感や痛みを覚えます。
さらに進行していくと軟骨がすり減っていき、クッションの役割を果たす組織がなくなります。
その結果、骨同士が接触し激しい痛みや腫れを伴います。
関節の変形
関節リウマチの初期段階で感じる違和感や痛みを放置しておくと、関節内部のダメージはさらに進行していきます。
やがて関節組織そのものが破壊され、本来の形を維持できなくなり大きく変形することがあります。
関節リウマチが進行した患者様の膝をレントゲンで撮影すると、膝の骨の一部が欠損していたり、膝が内側に折れ曲がったような形状になっているケースも少なくありません。
歩行困難
関節が変形するほど病気の進行を放置しておくと、最悪の場合、歩行そのものが困難になることもあります。
ここまで状態が悪化すると薬物療法やリハビリなどによる治療は困難となり、人工関節置換術でしか改善の見込みがなくなるケースも考えられます。
関連記事:関節リウマチは治るの?検査から診断基準、治療までの流れをご紹介
関節リウマチによる膝関節症の初期症状

関節リウマチと聞くと、手や足の指、手首など比較的小さな関節から症状が現れはじめるというイメージをもつ方も多いでしょう。
しかし、実際には膝や股関節など大きな部位から初期症状が現れ始め、徐々に末端の関節まで広がっていくケースも多いのです。
そのため、膝関節に以下のような症状が現れた場合、関節リウマチの初期症状の可能性が考えられます。
・膝全体が腫れ上がる
・膝に圧迫感を覚える
・階段の昇り降りや椅子から立ち上がるときに膝が痛む
上記の症状は、膝関節の内部にある滑膜とよばれる組織に炎症が起こり、水が溜まることで現れます。
滑膜の炎症はさまざまな要因によって引き起こされますが、そのひとつに免疫細胞の異常である関節リウマチも含まれるのです。
上記の初期症状が進行していくと、平坦な場所を歩行するときにも痛みが感じられるようになるため、早めの治療が必要です。
関連記事:関節リウマチかもしれない初期症状や変形性関節症との違いを解説!
関節リウマチによる膝関節症の治療方法

関節リウマチによって膝関節に異常が発生した場合、どのような治療法が考えられるのでしょうか。代表的な3つの方法をご紹介します。
薬物療法
関節リウマチと診断された場合、まず薬物療法を行います。
「メトトレキサート」という薬が現在、関節リウマチに対する第一選択薬として広く使われています。
免疫異常を抑え、炎症を止める効果にすぐれたお薬です。
病気の程度や合併症によっては、メトトレキサート以外の抗リウマチ薬を使用したり、組み合わせて服用したりすることもあります。
1~3か月ごとに病気の活動性をチェックし、効果が不十分な場合は、生物学的製剤と呼ばれる、より強力な抗リウマチ薬(注射製剤)の追加を検討します。
これは、単独で使われることもあります。
近年では、内服薬でも生物学的製剤と同等かそれ以上の効果が期待できるJAK阻害薬という薬も開発されています。
手術
上記でもご紹介した通り、関節リウマチによって膝関節の変形や歩行困難などのリスクが顕在化した場合には、外科手術によって人工関節を埋め込む治療が選択されるケースもあります。
また、関節リウマチそのものが初期段階であったとしても、加齢やその他の疾患によって関節の変形が認められる場合には、外科手術が適用される場合もあります。
リハビリテーション
長期間にわたって関節を動かさない状態が続くと本来の機能が失われ、関節そのものが固くなったり、最悪の場合、関節が変形し動かなくなることもあります。
これを防ぐためには、痛みがあったとしても少しずつトレーニングを続けていくことが重要です。
専門知識をもった理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションはもちろんのこと、自宅で手軽にできる体操やストレッチなども関節リウマチの立派な治療方法です。
関節リウマチで膝が痛いときはどうする?

膝関節に痛みがあり、関節リウマチが疑われる場合にはどういった対処が求められるのでしょうか。
早めに医療機関で診察を受けることは大前提として、自宅でできる対処法をご紹介します。
微熱・倦怠感があるとき
膝関節の痛みに加えて、37℃程度の微熱や全身の倦怠感がある場合には、無理に動かずに安静を心がけてください。
特に、痛みのある膝関節に大きな負荷をかけることは厳禁です。
痛みや微熱が落ち着いたとき
痛みや微熱が落ち着いてきたら、無理のない範囲で少しずつ体を動かしていきます。
急に大きな負荷をかけてしまうと状態を悪化させてしまうため、深呼吸をしながら慎重に膝の曲げ伸ばしを行ってください。
筋肉や腱は体が温まることで伸びやすくなるため、入浴後のトレーニングがおすすめです。
また、膝の状態によっても正しいトレーニングの方法は異なるため、必ず医療機関でリハビリや運動の方法を聞いたうえで実践するようにしましょう。
関節リウマチによる膝関節症のご相談はイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックまで
膝関節の痛みは、関節リウマチ以外にもさまざまな原因によって発症するため、まずは専門の医療機関で診察を受けることが大切です。
関節リウマチは多くの整形外科で診療が可能ですが、対応可能な治療方法は医療機関によっても異なります。
また、変形性膝関節症や半月板損傷など症状が似た疾患もあるため、信頼性の高いクリニックを選ぶことも重要といえるでしょう。
関節リウマチによる膝関節症にお悩みの方は、イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックまでご相談ください。
当院では関節専門外来を設置しており、関節リウマチをはじめとしたさまざまな疾患の検査・治療が可能です。
また、薬物療法はもちろんのこと、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション、さらに進行が進んだ患者様に向けて人工関節置換術にも対応できます。
関節リウマチによる膝関痛についてのまとめ
免疫疾患のひとつである関節リウマチを発症すると、関節に炎症が生じ痛みや腫れ、さらには関節の変形などを引き起こすリスクがあります。
膝関節のように大きな部位から発症するケースもあることから、痛みや違和感などを感じたら早めの検査・治療が必要です。
重症化すると人工関節置換術という外科手術でしか完治できなくなるケースもあり、その場合は対応できる医療機関も限られてしまいます。
信頼性が高くさまざまな治療法に対応している整形外科をお探しの方は、イノルト整形外科痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください。
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックのアクセスマップ
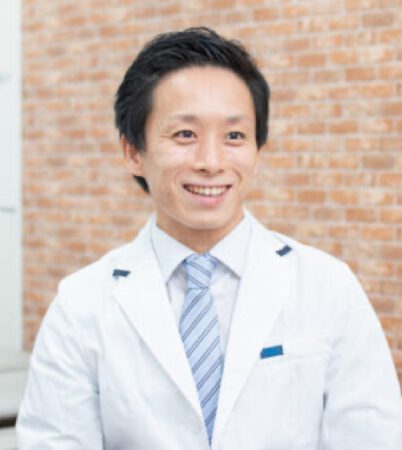
藤沢駅前 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長 渡邉 順哉
経歴
●東邦大学 医学部 卒業
●横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
●イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
理学療法士 皮膚運動について
フランスの理学療法では、創傷治癒 や美容において研 究が進んでいるが、運動学的見地からの情報が少ない。皮膚の運動において重要なことは、「皺線 ・緊張線・連続性」である現時点で え考えられている。皺線は、皮下の筋の走行と関連があると言われ筋の走行に直角方向に生じるものとされている。特に手術後の傷をあまり目立たくするためには皮切部位に皺線が重要。皺線に沿った瘢痕組織は生理的な膠原線維配列と同じ方向に治癒するために目立たなくなると考えられている。
皮膚のように関節運動に柔軟に対応している場合、それは骨運動に追随していると考えられている。皮膚が動く方向は皺が寄りにくい方向であった。実際に皺は生じるのであるが、寄ることが少なくなる方向に移動するのである。つまり皮膚には運動する方向があることになる 。
徒手にて皺のよる部分に対して伸張刺激を数十秒行うことで関節運動がやりやすくなる。あるいはテ ーピ ン グ をすることも可能である。テープは伸縮性、非伸縮性どちらでもよいが貼る際に皺が寄らないように、上腕で肩から肘方向へ 。体幹側では肩から体幹中央へという方向性が重要である。
次に緊張線は局所の皮膚をつまみ寄せたときにできる皺を観察して指の間にできる細かい皺が平行による方向を指す。弛緩した際のものであるため関節可動域の最終域で緊張線の方向が異なるように観察できる。皮膚と皮下
組織の相対的な位置関係が変化するために生じ、皮下の組織がその誘導された方向に動きやすいという特徴がある。
皮膚の運動学的特徴についてはまだ整理されているとは 言えないが今のところ次のように考えられている。
まず、緊張線について皮膚が伸張された肢位における緊張線が重要であると考えられている。特に関節可動域最 終域で皮膚が伸張されていることを考慮し運動時に操作するポイントとする。今後、臨床および研究両側面から皮膚の運 動をさらに深く追求されていくと考えます。術後に関節が動かなくなったり術後の切開瘢などが気にならなくなるような治療技術の進歩が期待できる。またそれを患者さまに還元できると理学療法士の需要もさらに高まると考えた。
理学療法士 肩関節 治療について
人の肩関節は四足獣と比較して明らかに異なる。肩甲骨は胸郭の左右への扁平化とともに後方へ移動し,上肢は背側へも動くようになった。荷重関節であった肩関節が,その役割から開放されたとき,劇的な変化を遂げたことは間違いない。筋の役割も大きく変わり,前鋸筋などは体幹を吊り下げる機能から,上肢を重力に逆らって挙上するための肩甲骨の上方回旋に寄与するようになった。祖先の形態とその機能を少しずつ変化させて適応しながら,このように大きな可動域を持つ関節となった。
筋による肩関節の安定化を考える場合には,回旋筋腱板の機能は重要である。筋力のバランスが崩れて inner muscle が outer muscle よりも相対的に弱化すると,上腕骨頭が十分に関節窩に引き付けられず,不安定性を助長することになる。外旋筋群はinner muscle が中心であるので,どの肢位での外旋運動でも棘下筋を強化することが可能である。下垂位(第 1 肢位)での外旋運動では,抵抗をかけずとも最終可動域まで動かすことにより,筋力強化に十分な筋収縮を得られることが明らかにされている。
肩甲上腕リズムに関して,肩甲骨の上方回旋を促すためには僧帽筋の各線維と前鋸筋のバランスよい筋活動が必要となる。多くの場合,僧帽筋上部線維の活動が過多となり,挙上運動が優位になることが多い。そこで,活動
を抑えた状態で中部線維,下部線維,前鋸筋の活動を高める運動を行うことが必要となる。筋力強化だけでは不十分であり,そのうえに運動学習を促す必要性がある。今後,肩甲上腕リズムの改善を目的とした選択的筋力トレーニング,さらには運動学習が患者さまの治療において重要となる。
肩関節が複雑な機構であるのも,重力との闘いの末に勝ち得た結果といえる。この神秘的ともいえる機構を再建するために,理学療法士に何が出来るのか,日々臨床のなかで今回の講習治療経験を活かしていきたい。
整形外科手術とリハビリテーション
前にすべきことは何でしょうか?
PTの関わり方次第で、予後が良くもなれば悪くもなるので手術に対する深い洞察はとても重要です。
深部静脈血栓症 (DVT) の成 因は「血液のうっ滞 ・血管内膜の損傷・血液凝固能の亢進」の 3原則が知られております。整形外科疾患術後においても下肢静脈の直接的損傷に加え、臥床による血液うっ滞から静脈血栓塞栓症(VTE )の発生頻度がきわめて高いため予防が必要です。下肢手術後のリハビリを担当する機会の多いPTは血栓症に十分な理解をしておく必要があるのです。
整形外科疾患の中でもDVTを生じやすい手術として、下肢の人工関節手術が知られておりTHA 後 で22% ,TKA後で50%とされています。
DVT予防として理学療法的手段には、術前からの足関節底背屈運動。術後早期からの関節可動域運動や筋力増強運動。早期離床などがあるのです。
整形外科術後のリスク管理には合併症に注意しながらの早期介人がすすめられる。よりよいアプローチを行うためには、常にリスクを理解し対応しなければいけないのです。運動機能ばかりに目を向けず,起こりうるリスク を理解し対処法を習得しておくことで、安全で安心な医療の提供に繋がるのです。
橈骨遠位端骨折のアプローチについて
橈骨は橈骨幹端から骨端にかけて骨皮質に急激な非薄化する。そこで生じる骨折のことを橈骨遠位端骨折。
ではなぜか骨折するか、サルコペニアや転倒しやすいからだ、栄養失調など。筋力機能低下に伴う環境背景が結果的に転倒しやすい体へ変化していくのです。
骨折の種類として、コーレス骨折(背側転位)とスミス骨折(掌側転位)があり、手もついての骨折が多いため【コーレス骨折】が多い。
術後は軟部組織の滑走が低下(癒着するため)、そのためどこで癒着しているか評価しないといけない。
例えば、手関節を背屈したときに制限がかかるが「手関節掌屈し手指MPjtが可動域上がる場合」は掌側側の軟部組織の癒着と考える。
また手関節掌屈した際のMPjtの制限あるが「背屈位でMPjtの可動域upの場合」は背側の前腕から近位部から手関節部の癒着と考える。
手術による影響として「浮腫も考えられる」
手術侵襲による皮膚損傷により硬化しその近くの静脈も影響を受ける。そのため心臓に帰る血液循環が悪化し浮腫になる。また骨折や外傷による深層組織損傷の場合微細動脈が圧迫影響を受け弾性力低下し「動脈内圧が上昇し循環器系に影響を及ぼし浮腫になりやすい。そのため、皮下組織の柔軟性獲得による静脈還流量の増大や疼痛に伴う血管収縮の抑制を改善しないといけない。
リハビリでは手指や手関節に制限をかけないように、持続強制プラスホットパックや温冷交代浴(温浴:4-5min冷浴:1min ※自律神経過反射を促さないように温浴で終わる)で循環改善することが求められる。
理学療法士 野球動作のバイオメカニズムについての勉強会
野球は、日本で最も人気のあるスポーツのひとつです。野球の動作には投・打・走・守・輔などがみられますが、このうち投球動作は野球を構成する最も重要な動作です.野球の投球動作には,守備位置別にみると,異なる運動課題(目的)が要求されます。すなわち,投手には打者をアウトにするためにストライクゾーンに直球や変化球を正確にかつ速く投げることが,捕手,内野手および外野手には打者走者をアウトにするために他の野手に,すばやい動作でボールを正確にかつ速く投げることが要求されます。このように野球の投球動作は,状況に応じた複数の課題が組み合わされていることがわかります。
投球障害肩・肘は,投球過多による軟部組織の過度な緊張や疲労を要因とし,その状態でも繰り返し投げ続けることにより発症する身近な問題です。投球動作のバイオメカニクスでは,投球障害リスクの最小化および投球パフォーマンスの最大化を定量的にめざす。投球障害に至った投手はそうとはならなかった投手よりも,投球動作中の関節にかかる大きなトルクが加わわり,関節に加わる力やトルクの大きさを関節への負担(障害リスク)の大きさととらえる。
そのため、,投球動作中の関節に加わる力とトルクをできる限り低減させ,球速やコントロール,あるいはその両者を維持する/向上させる投球動作を探索することが,投球動作のバイオメカニクスの道筋として重要です。
投球障害肩肘と関連づけられている投球動作中の力とトルクの多くは、「コッキング相から加速・減速相」に当てはまる。(特にコッキング相後半と減速相からフォロースルー相前半には,肩関節と肘関節に大きな多様な負担が加わる)
リハビリでは、オーバーヘッドスポーツ(野球やバレーボールなど)における下肢・体幹・肩甲胸郭関節での運動連鎖では下肢の柔軟性低下・体幹の可動性低下が生じると肩甲胸郭関節(肩甲骨)などで過剰な代償が生じる可能性があるのです。再発防止のためにはこれらの機能改善も必要と考えているためエクササイズで柔軟性の獲得は必須事項となります。
触診勉強会を実施しました。
スポーツ整形外科に多い疾患は?名医の特徴や整形外科との違いを解説

プロのアスリートやスポーツの愛好家のなかには、ハードなトレーニングやプレーによってケガをしたり、障害を負ったりすることがあります。
そのような場合において、早期の治療と競技への復帰をサポートするのがスポーツ整形外科という専門の診療科です。
本記事では、そもそもスポーツ整形外科ではどのような疾患の治療が可能なのか、一般的な整形外科との違いや信頼できるクリニックの特徴・選び方などもあわせてご紹介します。
スポーツ整形外科とは?

スポーツ整形外科とは、その名の通りスポーツによって発症しやすい疾患を扱う診療科のことです。
プロのアスリートはもちろん、趣味でスポーツを楽しんでいる方の中には、身体を酷使するあまり外傷や障害を負うことも少なくありません。
早期に復帰するためには、専門的な知識や治療・リハビリのサポート経験が不可欠であり、これらに特化しているのがスポーツ整形外科です。
スポーツによって生じることの多い外傷としては、肉離れや疲労骨折、アキレス腱の断裂などが挙げられますが、これらは日常生活のなかでも負傷するリスクがあります。
そのため、スポーツ整形外科の多くは、スポーツによって生じた外傷や障害以外の治療にも対応しています。
スポーツ整形外科と整形外科の違い
スポーツ整形外科と一般的な整形外科にはどのような違いがあるのでしょうか。
スポーツに関する専門知識の有無
整形外科と聞くと骨折や捻挫などの外傷を専門としているイメージがあり、スポーツ整形外科もこれらの治療が可能です。
しかし、両者の違いを一言で表すとすれば、スポーツに関する専門知識の有無でしょう。
スポーツ整形外科の専門医は、アスリートのサポートや担当医としての経験が豊富にあり、スポーツに関する専門知識を持ち合わせています。
そのため、競技においてケガのリスクが少ない身体の使い方やリハビリの方法など、専門的なアドバイスも可能です。
治療の目的・ゴールの違い
一般的な整形外科の場合、患者の多くはアスリートではない一般の方であるため、「立つ・座る・歩く」などの基本的な日常生活が送れるようになることが治療のゴールとなります。
しかし、スポーツ整形外科ではアスリートが競技に復帰できることが前提となるため、その個々の競技におけるハードなトレーニングや試合においても怪我や故障の再発を防ぎつつ、怪我や故障の前の状態以上に競技パフォーマンを上げられるようにサポートをしなければなりません。
スポーツ整形外科が扱う代表的な疾患

スポーツ整形外科ではさまざまな外傷・障害の治療にあたりますが、そのなかでも代表的な疾患をいくつかご紹介しましょう。
野球肘
野球肘は野球の投手が多く発症する疾患で、ボールを投げたときに肘の内側や外側などに痛みが生じます。身体が固い状態で、無理なフォームでボールを投げたり、練習のしすぎによって肘に負荷がかかることで発症することが多い疾患です。
テニス肘・ゴルフ肘
テニス肘はラケットを握る利き手の肘に痛みが生じる疾患です。肘の外側部分に痛みを生じた場合を上腕骨外側上顆炎(テニス肘)と呼び、無理なフォームや過剰な負荷によって炎症や痛みが生じます。逆に肘の内側に痛みが出た場合を上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)と呼び、こちらも特に多い病気の一つです。
▶テニス肘の治し方!自分で治す方法は?整形外科での治療法を解説
前十字靱帯損傷
前十字靱帯損傷は、バスケットボールやサッカーなど、ジャンプの動きを頻繁に繰り返す競技において発症しやすい膝の怪我です。また、急な方向転換などによって膝に負担がかかった場合にも発症することがあります。
半月板損傷
半月板損傷も、ジャンプや急な方向転換などによって膝に強い捻じれ負荷がかかった場合に発症しやすい疾患です。膝に痛みや違和感を覚えるようになり、適切な治療を行わないと膝に水が溜まり曲げ伸ばしが困難になることもあります。
▶半月板損傷とはどんな状態?原因や症状、治療について詳しく解説!
▶半月板損傷でやってはいけないこととは?早く治す方法も解説!
▶半月板損傷を早く治す方法や症状が改善するリハビリについて解説
ジャンパー膝
ジャンパー膝は「ジャンパーズニー」あるいは「膝蓋腱炎(膝蓋靭帯炎)」ともよばれる膝の疾患です。バスケットボールやサッカーなどジャンプを頻繁にする競技で発症リスクが高く、お皿の骨(膝蓋骨)からすね(脛骨)に伸びる腱にわずかな亀裂が入りそこで痛みや炎症が長期化していきます。
オスグッド病
オスグッド病とは、成長期にある子どもに多く見られる疾患のひとつです。特に思春期に身長が伸びるスピードが早いと、骨の成長に伴い筋肉の柔軟性が失われ、膝の部分の骨が盛り上がったようになり痛みを感じます。特に運動中や運動後に痛みが強く現れやすい傾向があります。
ランナー膝
ランナー膝は別名「腸脛靱帯炎」ともよばれ、ランニングによって発症しやすい膝の代表的な疾患です。ランニングによって膝の曲げ伸ばしを繰り返していると、太ももの外側から膝関節に伸びる腸脛靱帯が大腿骨に接触し炎症を起こし痛みを感じるようになります。
ランナー膝は長距離ランナーに発症しやすい傾向がありますが、そのほかにも自転車競技やエアロビクスなどでも発症する場合があります。
肉離れ
肉離れの正式名称は「筋挫傷」とよばれ、筋肉の線維や筋膜の一部が断裂あるいは損傷した状態を指します。身体の酷使によって疲労が蓄積している場合や、加齢、準備運動の不足によって発症しやすく、あらゆるスポーツ競技において発症リスクがあります。
肉離れが起こる部位はさまざまですが、なかでも太ももの裏やふくらはぎなど、下半身に発症するケースが多いです。
疲労骨折
疲労骨折とは、特定の部位にわずかな衝撃や負荷がかかり続けることで生じる骨折です。
一般的な骨折とは異なり目立った腫れや皮下出血、痛みなどが見られないことがあり、はじめのうちは骨折に気づかないことも多いようです。
しかし、日常的に競技を続けるなかで骨の損傷が拡大していき、徐々に痛みが強くなり競技継続が困難になることも珍しくありません。
捻挫
捻挫は関節に無理な力が加わることによって、関節を支える靭帯や腱、軟骨などが損傷する場合があります。特に多い足首の捻挫はスポーツの競技中はもちろん、交通事故や階段の昇り降り、転倒などによっても起こるケースが多いです。
膝蓋骨脱臼
膝蓋骨脱臼は、いわゆる膝の皿とよばれる膝蓋骨が外れる疾患です。
膝を伸ばした状態のときに足全体をねじる動作をとったときや、膝のお皿の骨を内側から強打した場合などに発症することが多いです。膝蓋骨脱臼を一度発症すると、その後脱臼を繰り返すケースが少なくありません。
スポーツ整形外科の名医の特徴

信頼できるスポーツ整形外科には名医とよばれるドクターが在籍していることが多いものです。スポーツ整形外科の名医にはどのような特徴があるのか、信頼できるクリニックの選び方もあわせてご紹介しましょう。
アスリートへのサポート経験が豊富
スポーツ整形外科の医師のなかには、過去にプロスポーツチームの専属ドクターを務めていたり、リハビリをサポートしていたなどの経験・実績が豊富なドクターもいます。
このような経験によって、アスリートが負傷しやすい部位や疾患を熟知しており、早期回復と競技への復帰をサポートできます。
多様な疾患の治療経験・実績がある
上記でも紹介したように、スポーツの競技によっても疾患の種類は多様であり、それぞれ治療法も異なります。
信頼性の高いスポーツ整形外科は、さまざまな疾患の治療経験が豊富で、早期回復につなげるためのノウハウや知見を持ち合わせています。
また、一般的な整形外科とは異なり、競技への復帰を最終的なゴールとしているスポーツ整形外科では、健康保険が適用されない自由診療も含め最新の治療法に対応していることも多いです。
アスリートからの信頼が高い
スポーツ整形外科に限ったことではありませんが、信頼できる医療機関や名医を探すためには、実際にそのクリニックを受診したことのある患者からの口コミや意見を参考にするのも重要です。スポーツ整形外科の場合、多くのアスリートから選ばれているクリニックほど信頼性が高い傾向があるでしょう。
スポーツ整形外科の主な治療方法

スポーツ整形外科では具体的にどのような治療法に対応しているのでしょうか。代表的な治療法をいくつかご紹介します。
運動器リハビリ
運動器リハビリとは、いわゆる一般的なリハビリテーションのことを指します。靭帯や腱などを損傷すると関節の曲げ伸ばしが困難になり、可動域が狭まったり筋力が落ちてしまったりしますが、これらを改善するために運動器リハビリが行われます。
ストレッチや筋力強化はもちろん、温熱や電気を使用した物理療法、専用の装具によって固定しながら行うリハビリもあります。
再生医療
再生医療とは、私たちの体内にある一部の組織を利用し、病気やケガなどの疾患によって機能不全に陥った組織を再生する治療法のことです。
スポーツ整形外科の分野では、血液の中から血小板が多く含まれる成分を抽出し、患部に注入する「PRP(多血小板血漿)療法」や、脂肪などに含まれる赤ちゃん細胞となる幹細胞を取り出し培養した後、患部に注入する「幹細胞治療」などがあります。
▶PRP療法の注射が膝や股関節に効果的な理由とは?副作用はある?
体外衝撃波
体外衝撃波は、特殊な専用の機器を用いて患部に衝撃波を照射し、関節部の痛みや炎症を緩和する治療法です。もともと尿路結石の破砕に用いられていましたが、近年では整形外科の分野でも痛みや組織の修復のための治療器として使われるようになりました。
拡散型と集束型の二種類があり、より集束型の方が痛みを取り除き、組織を修復する能力に長けています。
▶体外衝撃波は治療効果がない人はいる?|適切な治療回数や痛みについて
薬物療法
薬物療法は、内服薬や外用薬によって痛みや炎症を鎮める治療法です。
捻挫や打撲などを負い整形外科を受診したときに、湿布薬や痛み止めを処方された経験がある方も多いと思いますが、これらは代表的な薬物療法です。急性期の短期間に痛み止めを使うこともあります。
物理療法
物理療法とは、関節を引っ張ったり電気や温熱などを与えたりすることで血行を改善し、痛みや炎症を緩和する治療法です。
クリニックによってもさまざまな治療法があり、症状や患部の状態に合わせて適切な治療法が選択されます。理学療法士のリハビリがまだ珍しい時代に代替療法として始まった治療法のため、特に温熱療法や牽引治療は効果の面でもやや陳腐化しつつあります。
一方で、超音波治療器や低周波治療器は弱いながらも一定の治療効果を認めています。
装具療法
装具療法とは、膝や腕、腰、首などの患部を専用の装具によって固定し、痛みや炎症の悪化を抑えたり、損傷した靱帯などの治癒までに患部の安静を保つための保存療法のひとつです。
骨折をした際にギプスやコルセットで固定するのも装具療法のひとつであり、症状にあわせてサポーターやテーピングなど最適な装具を選択します。
しかし、本来固定されていない関節を固定してしまうことで関節は固くなり、筋力も落ちるため、長期使用に対しては慎重になる必要があります。
スポーツ整形外科をお探しの方はイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへ
一般的なクリニックや総合病院などには整形外科がありますが、スポーツ整形外科に対応している医療機関は限られています。そのため、スポーツで負傷したケガを治療したい方や、ケガを未然に防止するための専門的なアドバイスを受けたい方などは、どの医師に相談すれば良いのか分からないことも多いでしょう。
もしそのようなお悩みを抱えている場合には、ぜひ一度イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックにご相談ください。
院長の渡邉順哉医師は現役の空手選手であり、さまざまな試合に出場しているほか大会救護ドクターとしても活動しています。
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックのスポーツ整形外科では、空手師範や空手指導者はもちろんのこと、プロゴルファーやプロサーファー、重量挙げ選手などさまざまなアスリートが治療を受けています。
まとめ
野球肘やテニス肘、ジャンパー膝、ランナー膝など、日々ハードなトレーニングを積んでいるアスリートだからこそ発症しやすいケガや障害は多いものです。
これらは一般的な整形外科でも治療することはできますが、ベストなコンディションを取り戻し早期に競技の場へ復帰するためには、専門的な知見のあるスポーツ整形外科を受診することがおすすめです。
スポーツ整形外科に対応しているクリニックは決して多くないため、もし近所で見つからない場合にはイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックへご相談ください。
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックのアクセスマップ
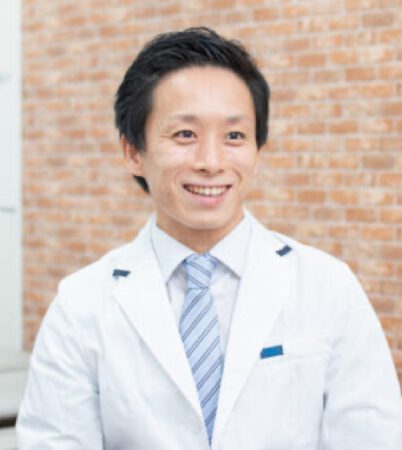
藤沢駅前 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長 渡邉 順哉
経歴
●東邦大学 医学部 卒業
●横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
●イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
理学療法士 勉強会 呼吸コンディショニング
人はこの世に誕生した時には「息を吐いて」生まれ、「息を吸う (引きとる) 」この世を去る。
人は呼吸をしてこの世を生きている。
正常でも、10から15回の呼吸を繰り返し1日当たり少なくとも14400回呼吸を行っている。その呼吸が正常でないと生活の質が落ちてくる。
例えばマラソン選手。最初は身体はブレなく走っているがゴール近くでは身体フラフラで呼吸も荒い。
またストレッチをしている時や筋トレをしている時、呼吸が止まるように。
呼吸と姿勢安定化は常に共存関係にあるが一緒に使用出来ないと、日常生活には落とし込めない。なぜかと言うと呼吸が止まるような姿勢には脳は動きの許可を出さないからです。
体が認知している効率良い姿勢(呼吸がしやすい)保持の癖があり最優先は呼吸。猫背の人はスマホやデスクワークが原因もあるが、長時間の姿勢保持よりも呼吸がしやすい姿勢を脳が選択し行っている。
その身体をいかに正常なアライメント(姿勢保持)ができるように組み立てていくかはコルセットの役割をしている「腹腔内圧(IAP)」の機能向上です。
横隔膜、多裂筋、骨盤底筋群また腹横筋の協調的な運動が必要になってきます。その協調的な運動がとても上手く機能しているのが赤ちゃんです。筋力はとても弱いのに対して四つ這い運動を軽々と行っている姿はいかに最初エネルギーで活動出来ているんだと思っております。
安静時の人の呼吸は、吸う方はうまいものの吐くのは横隔膜の弛緩によるものの為、あまり意識しなくても息を吐く動きが出来てしまう。そのため肋骨の絞る動きが少ないためコルセットでいう横側の圧が少ない。腹腔内圧が低下して肩呼吸のような吸う動き優位の姿勢になってしまう。イコール肩こりにも繋がる。
そのため、腹腔内圧を高めて良好な姿勢保持につなげるためにも呼吸コンディショニングが重要です。
理学療法士 勉強会 肩甲胸郭関節
今回は、肩甲胸郭関節の基礎についてお話しします。
肩関節は肩甲骨・鎖骨・上腕骨・胸郭から構成され、解剖学的肩関節と機能的肩関節に分けられます。
解剖学的肩関節には肩甲上腕関節・胸鎖関節・肩鎖関節があり、機能的肩関節には第二肩関節・肩甲胸郭関節があります。
肩甲胸郭関節は肩関節運動において非常に重要な働きを行います。
皆さんもご存じの通り、肩屈曲時の肩甲上腕リズムでは2:1の割合で肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節が動きます。肩を180°屈曲する場合では肩甲上腕関節が120°動き、肩甲胸郭関節が60°動くということになります。このことを考慮すると、最終域までの可動性を出すためには肩甲上腕関節、肩甲胸郭関節どちらもアプローチしていくことが重要だとわかります。
肩関節周囲炎において肩甲胸郭関節へのアプローチは炎症期の時期に積極的に行います。
肩関節周囲炎には炎症期・拘縮期・回復期という経過があり、炎症期では患部(肩甲上腕関節・第二肩関節)の安静、患部外(肩甲胸郭関節・肩鎖関節・胸鎖関節)の機能向上が必要になります。患部外の運動時に患部にストレスをかけないように介入していくことがポイントとなります。
また、術後のリハビリでも患部には安静度があるため肩甲胸郭関節へのアプローチを行います。
肩甲胸郭関節の動態は、肩鎖関節軸と胸鎖関節軸によって起こります。肩甲胸郭関節動態を見ていくうえで胸骨・鎖骨・肩甲骨・胸郭の動きを知る必要があります。
まずは鎖骨の動態についてです。
挙上時の鎖骨の動態を三次元的に見ると、挙上・後退・後方回旋が生じており、僧帽筋の上部線維が主動作筋として働きます。反対に拮抗筋として働く筋として鎖骨下筋・大胸筋鎖骨部線維・三角筋前部線維があります。挙上時に鎖骨の動きが制限されている際は拮抗筋へのアプローチをしていく必要があります。
次に肩甲骨の動態についてみていきます。
肩甲骨は肩関節挙上に伴い上方回旋・後傾・外旋します。
上方回旋の主動作筋は僧帽筋(上部線維・中部線維・下部線維)・前鋸筋下部筋束であり、拮抗筋は小胸筋・肩甲挙筋・小菱形筋・大菱形筋になります。
外旋の主動作筋は僧帽筋中部線維・前鋸筋中部筋束・小菱形筋・大菱形筋、拮抗筋は小胸筋・大胸筋。
後傾の主動作筋は僧帽筋下部線維・前鋸筋下部筋束、拮抗筋は小胸筋・烏口腕筋・上腕二頭筋短頭になります。
この肩甲骨の動きの中でいずれも、拮抗筋として小胸筋があることがわかります。このことから挙上動作において小胸筋の短縮は悪影響を及ぼす可能性があると考えられます。
挙上動作時に肩甲骨にフォーカスして見ていくと上方回旋・後傾・外旋が生じ、主動作筋である僧帽筋・前鋸筋の賦活化、肩甲骨動態すべての拮抗筋として働く(制限となる)小胸筋の柔軟性・伸張性の向上を狙ったアプローチをしていくことが重要となります。
最後に胸椎・胸郭について見ていくと、肩関節挙上に伴い胸椎は伸展、胸郭は挙上します。胸椎はTh3~6が動き、Th5が最大に可動します。Th5の可動域向上のためにはTh6を固定した状態で胸椎伸展運動を実施していくとTh5の伸展を誘導することができます。また、キャット&ドッグも運動療法として取り入れていくことで胸椎・胸郭の可動性向上が見込めます。