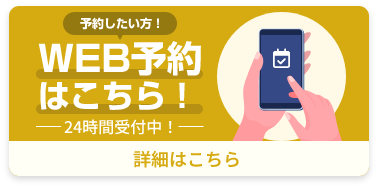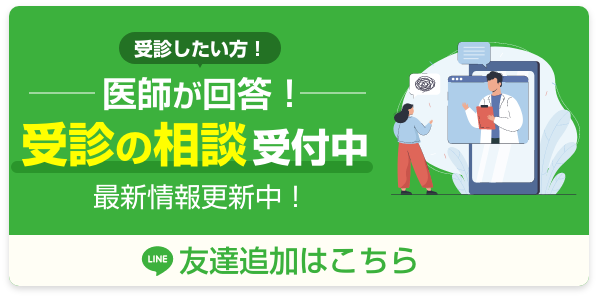変形性膝関節症の症状と対処法|進行を防ぐために知っておきたいこと
※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。

変形性膝関節症は、膝の関節軟骨がすり減ることで痛みや変形を引き起こす病気です。
初期段階では痛みが一時的に引くこともあり軽視されがちですが、知らないうちに進行していることも少なくありません。
本記事では変形性膝関節症の症状や信仰の目安・治療法などを詳しくご紹介します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
Contents
変形性膝関節症とは
変形性膝関節症とは、加齢や過度な関節への負担によって関節内の軟骨がすり減り、最終的には骨同士が擦れあったりすることで痛みや炎症を引き起こす疾患です。
筋力低下だけでなくホルモンバランスも影響しており、中高年の中でも女性に多くみられるとされています。
初期には違和感程度だった痛みが、進行することで歩行が困難なレベルになることもあります。
年齢のせいだからと決めつけることなく、早期に医療機関を受診することで、軽度のうちに適切な治療を受けられます。
変形性膝関節症の主な症状と進行の目安

変形性膝関節症の症状は進行段階によって異なります。
初期症状|こわばり・違和感・動き始めの痛み
朝起きたときや椅子から立ち上がった瞬間に膝がこわばるなど、違和感や不快感からスタートするケースがほとんどです。
単に歩くだけでは痛みを感じないことも多く、医療機関の受診を後回しにしてしまう方も少なくありません。
中期以降の症状|階段や歩行に支障が出る
階段の昇り降りや長時間の歩行時に痛みが強くなり、日常生活に支障をきたし始めます。
膝に水が溜まったり、外側から見て分かるレベルに腫れたりといった症状も見られます。
進行度によって変わる膝の見た目や動き方
関節の変形が進むと、O脚やX脚など脚の見た目が変化することがあります。
可動域が大きく制限されることから、正座やしゃがむ動作などが困難になります。
関連記事:膝の痛みで病院に行くタイミングとは?治療と再発予防のポイントを解説
変形性膝関節症と似た症状を持つ疾患
変形性膝関節症以外にも、膝に痛みを生じる疾患があります。
半月板損傷
スポーツや転倒などの外傷が原因となる場合だけでなく、加齢による劣化によって日常生活動作だけでも損傷することで発症します。
膝の中で引っかかるような感覚があったり、断裂した半月板が関節に挟まって動かなくなる「ロッキング現象」が起こったりすることもあります。
多くの場合で強い痛みを生じるほか、腫れや水が溜まるなど外側から見た変化が起きやすく、放置すると変形性膝関節症に進行しやすい疾患でもあります。
鵞足炎
鵞足炎(がそくえん)は膝の内側下方にある骨の周囲に炎症が生じる疾患です。
スポーツなど定期的な運動によって起こりやすく、患部を押したときに痛みが強くなるのが特徴です。
大腿後面の筋肉が固くなると発症しやすくなり、変形性膝関節症の患者様にも鵞足炎を併発している方が多く見られます。
関節リウマチ
関節に炎症が起き、軟骨や骨が次第に破壊されてしまう疾患です。
膝だけでなくあらゆる関節で起こる可能性があり、左右同時に発症することもあります。
他の疾患が動作時に痛みが強まるのに対し、関節リウマチは安静時でも強い痛みを感じます。
膝のような大きな関節のみに発症することは珍しく、多くの場合は手や足の指などの小さな関節に発症し診断されることが多いです。
変形性膝関節症を悪化させないためにできること
変形性膝関節症と診断された場合、日常生活での工夫が進行を遅らせるポイントとなります。
適切な体重管理
体重が増えると、膝にかかる負担が増大します。
身長に対する適正体重を保ち、膝関節へのストレスを可能な限り軽減してあげることが大切です。
標準体重(BMI=22)を目指すために、食事の内容を適切に管理し、運動量も増やすことで摂取カロリーの削減と消費カロリーの増加を行う必要があります。
膝に負担をかけない
長時間の正座やしゃがみ込むような動作、坂道や階段の頻繁な利用は、膝に負担がかかります。
座るときは地面でなく椅子を使ったり、商業施設ではエレベーターやエスカレーターを利用したり、登山や走り回る競技などで膝を酷使しすぎないように膝を労わる生活習慣を身につけましょう。
筋力トレーニングやストレッチ
太ももやお尻の筋肉を鍛えることにより、連動している膝関節のサポートにつながります。
凝り固まった膝関節周囲の筋肉はストレッチによって柔軟性を保ち、痛みの悪化・予防を目指しましょう。
関連記事:変形性膝関節症の原因とは?初期症状や進行度についても解説
変形性膝関節症の治療法
整形外科では、症状の程度に応じて、保存療法から手術までさまざまな選択肢を用意しています。
理学療法士の施術
関節の動きをなめらかに保ちつつ、筋力アップを目指すためのリハビリテーションが行われます。
長期間続けることにより、痛みの緩和だけでなく、再発や他の疾患を予防することにもつながります。
最も根本的な治療ですが、一度の治療で治るものではないため、毎週1~2回を半年程度継続する必要があります。
薬物療法(内服、外用、ヒアルロン酸注射)
消炎鎮痛剤や外用薬・関節内注射によって痛みのコントロールを図ります。
いずれも効果が一時的であることも多いため、定期的な診察を受け、痛みの変化を確認していく必要があります。
ヒアルロン酸注射も昨今見直されて、痛みを緩和する効果がある程度は期待できる治療になります。
ハイドロリリース
筋膜や神経の周辺に生理食塩水を注射することにより、癒着した細胞同士を引きはがし、なめらかな動きを取り戻すため注射です。
変形性膝関節症で膝の内側が痛い場合は、内側側副靭帯上に注射を行うと、多くのケースで痛みが軽減します。
生理食塩水を使用するため異物への拒否反応が起こりにくいといった利点があります。
体外衝撃波治療(拡散型、集束型)
空気を圧力によって押し出すことで末梢神経を麻痺させ、痛みの緩和を図ります。
同時に血流の改善が期待でき、組織の修復が加速化する点もメリットといえます。
一点に高いエネルギーを集中させる「集束型」と、広い面にエネルギーを分散させる「拡散型」があり、変形性膝関節症の場合は、関節内症状のため深部まで強力な衝撃波が届く集束型体外衝撃波の方がより高い効果が得られやすいです。
再生医療(幹細胞治療、成長因子療法、幹細胞上清液療法)
自身の血液や細胞を採取して患部へ注入することにより、組織の修復を加速化させたり、炎症を抑えたりするための施術です。
人体に備わっている自然治癒力がアップすることから、症状の進行を抑える効果が期待できます。
理学療法士の治療は関節外の関節を支えたりする筋力や姿勢などを改善するのに対し、再生医療は関節内の状態の悪化を防いだり、一部では修復してくれるはたらきがあります。
症状の悪化を防ぎ、手術を回避できる場合も多い治療法です。
手術療法(TKA、UKA、骨切り)
症状が進行し上記の施術では改善が難しいと判断された場合は、人工関節置換術(TKA・UKA)や骨切り術が検討されます。
骨切りは内側か外側いずれかの軟骨が健在している場合に可能で、UKA(単顆人工膝関節置換術)のように置換が一部で済む場合もあれば、変形性膝関節症が進行している場合はTKA(人工膝関節全置換術)のように全てを入れ替えなければならない場合もあります。
関連記事:年代別に膝の痛みの症状をチェック|考えられる疾患や受診の目安は?
変形性膝関節症でお悩みの方はイノルト整形外科まで
膝の痛みにお悩みの方は、イノルト整形外科の受診をご検討ください。
当院では、患者様の状態に合わせた検査・治療が可能です。
レントゲンや超音波・MRIを用いた正確な診断を経た後、再生医療・体外衝撃波・理学療法士の治療・ハイドロリリースなど幅広い保存療法を選択し、手術を受けずとも痛みの改善を目指します。
さらに、必要に応じて専門手術が得意な医療機関と連携しながら、患者様が快適に日常を過ごすためのサポートを行います。
まずはお近くのクリニックへご相談ください。
まとめ
変形性膝関節症は、早期発見と適切な処置が重要です。
症状に合わせたセルフケアと医療機関での治療をうまく組み合わせ、進行を抑えながら生活の質を保ちましょう。
変形性膝関節症が疑わしい方や、変形性膝関節症など膝の痛みにお悩みの方は、ぜひイノルト整形外科痛みと骨粗鬆症クリニックまでお気軽にご相談ください。
この記事の監修医師
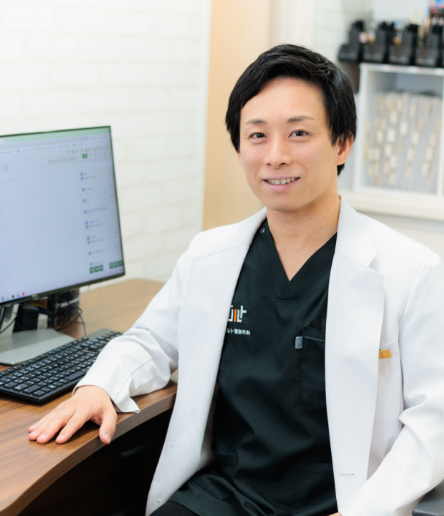
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
渡邉 順哉
経歴
- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒
- 平成23年 東邦大学 医学部卒
- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修
- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科
- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長
- 平成30年 渡辺整形外科 副院長
- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長
- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長