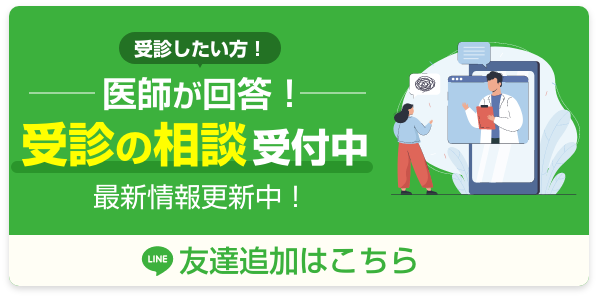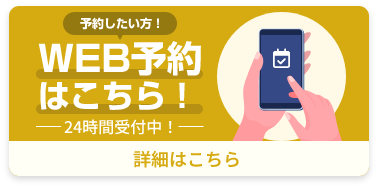膝の水を抜く方法は?効果のあるストレッチや予防方法を紹介
※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。
今回ご紹介した内容を参考に、膝に水が溜まっているかもしれないと感じた方は、まずは早めにイノルト整形外科へご相談ください。
加齢やケガ、激しい運動、体重増加などが原因で膝に水が溜まることがあります。
このような場合、膝の水を抜く治療が行われますが、再発を防ぐためにもさまざまな治療法が検討されます。
本記事では、膝に水が溜まった際の治療法や予防法の一例、日常生活でも実践できるストレッチやトレーニングの方法なども詳しくご紹介します。
◆イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックの関節専門外来はこちら◆
Contents
膝に水が溜まる原因は?
そもそも膝の水の正体は、関節内に存在する「関節液」のことです。
関節液は本来、関節のスムーズな動きをサポートする重要な役割を担っていますが、何らかの原因によって分泌量が異常に増えることがあるのです。
では、主にどのような原因で膝に水が溜まるのでしょうか。代表的な疾患をいくつかご紹介します。
変形性膝関節症
運動のしすぎや加齢、体重増加などによって膝関節に大きな負担がかかり、軟骨などの関節組織が摩耗することで炎症や痛みを引き起こすのが変形性膝関節症です。
特に変形性膝関節症の炎症で関節液が溜まったり改善したりを繰り返し、これを放置しておくとさらに症状が悪化し、最悪の場合関節そのものが変形したり歩行やしゃがみ動作が困難になるケースもあります。
なお、膝関節内から抜いた関節液が透明な黄色をしている場合、変形性膝関節症の可能性が考えられます。
半月板損傷
ジャンプや急な方向転換などを伴う激しい運動をしていると、関節内の半月板という組織が損傷し炎症や痛みを伴うことがあります。
また、加齢に伴い、立ち上がり動作など日常生活動作だけでも損傷を起こす場合もあります。
関節内に炎症が生じると関節液が過剰に分泌され、結果として膝に水が溜まりやすくなります。
変形性膝関節症は中年から高齢者が発症するケースが多いですが、半月板損傷は激しいスポーツをする若年層にも多いのが特徴です。
前十字靱帯損傷・後十字靱帯損傷
半月板損傷と同様に、激しいスポーツによって発症しやすいのが前十字靱帯損傷・後十字靱帯損傷です。
膝関節に強い力が加わると、前十字靭帯と後十字靭帯という組織が断裂し激しい痛みや腫れ、炎症が現れます。
なお、膝から抜いた関節液が怪我した直後だと赤色もしくは褐色の場合があります。
その場合は前十字靱帯損傷や後十字靱帯損傷、半月板損傷の可能性が考えられます。
関節リウマチ
リウマチとは免疫疾患のひとつで、膝関節以外にも体のさまざまな部位に発症するケースが見られます。
免疫機能に異常が発生し、本来正常であるはずの関節組織を破壊し重度の炎症や痛みを引き起こします。
関節リウマチは左右の関節に症状が現れるケースが多く、治療をしないまま放置しておくと日常生活にも支障をきたすほど重症化するおそれがあるため早期の治療が必要です。
なお、関節リウマチが原因で膝に水が溜まっている場合、関節液は濁った黄色になることがあります。
膝に水が溜まった時に受診すべきタイミング
膝に水が溜まっている場合、膝を曲げたときに突っ張っているような感覚を覚えたり、曲げ伸ばしがしにくくなったりすることがあります。
激しいスポーツをしたり、膝に大きな力や衝撃が加わったという覚えがなくても膝関節内部に異常が発生している可能性もあることから、上記のような症状が見られる場合には早めに医療機関を受診し必要な処置をしてもらうことが大切です。
受診するタイミングが遅くなるとさらに炎症が悪化していき、歩行が困難になるほど重症化する可能性もあるため注意しましょう。
膝に水が溜まったときに有効な治療方法

膝に水が溜まった場合、医療機関ではどのような治療法を行うのでしょうか。代表的な治療法をいくつかご紹介します。
関節穿刺(膝の水を抜く)
関節穿刺とは、いわゆる膝に溜まった水を抜く治療法です。
膝関節を伸ばした状態で関節内に注射針を刺し、過剰に分泌された関節液を抜きます。
特に関節液が過剰に分泌され、膝の曲げ伸ばしがしにくかったり、痛みや違和感を感じる場合に注射をして関節液を取り出すことで症状を緩和できます。
膝関節内部にはさまざまな神経や血管があるため、注射をする際にはこれらを避けて慎重に行う必要があります。
保存療法
症状が比較的軽度で、痛みや炎症を抑えたい場合には関節穿刺と併せて保存療法が用いられます。
主に痛み止めの飲み薬や湿布などの外用薬などが処方され、これらを用いることで炎症が緩和され関節液の過剰分泌も抑えられる可能性があります。
変形性膝関節症や半月板損傷の場合は、再生医療の治療法が有効になりやすいです。
注射療法
症状が比較的軽度の場合、保存療法と同様に用いられることの多いのが注射療法です。
変形性膝関節症や半月板損傷の場合は、ヒアルロン酸などを関節内部に注射することにより、損傷した部位のスムーズな動きをサポートし痛みや炎症を緩和できる可能性があります。
理学療法士によるリハビリテーション
膝関節の負担を減らそうとするあまり運動量が減ってしまうと、関節周辺の筋肉量が低下し関節を安定的に支えることができなくなります。
その結果、膝関節に無理な力が加わるようになり、一時的に症状が緩和できたとしても再発する可能性があるのです。
理学療法士の指導の下、適切なリハビリテーションを行うことで筋力がアップし、膝関節の安定性が確保され症状の再発を防げます。
手術療法
変形性膝関節症や半月板損傷、前十字靱帯損傷・後十字靱帯損傷、リウマチなどが原因で特に症状が進行している場合には、手術療法が用いられることがあります。
ほかの治療法に比べて入院期間やリハビリ期間が長く費用もかかりますが、高い治療効果が見込めることが多いです。
再生医療
新たな治療法として近年注目されているのが再生医療です。
患者様から取り出した細胞を培養、もしくは血液中の組織を修復する細胞を抽出し、それを膝関節に注射することで損傷した軟骨や腱の組織が再生されやすくなり、本来の機能を取り戻します。
ただし、すべてのケースにおいて再生医療が適用されるとは限らず、基本的には自由診療となるため高額な治療費が発生します。
膝の水を抜いた後の注意したい合併症
膝に水が溜まった際には、水を抜くことである程度の症状を緩和できます。
ただし、治療をきっかけにさまざまな合併症を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。
感染症
関節穿刺を行った際、膝関節内に細菌が侵入し感染症を引き起こす可能性があるため、穿刺前の消毒は入念に行なう必要があります。
通常、関節穿刺の直後は一時的な痛みや腫れが起こりますが、数日経っても痛みが引かず、腫れや炎症、熱を持っている場合には感染症を引き起こしている可能性が考えられます。
出血
関節穿刺は神経や血管を避けて施術を行いますが、施術ミスによって太い血管を傷つけてしまうと出血を伴うことがあります。
一時的に出血が見られる場合でも患部を圧迫すれば自然と血が止まりますが、数時間経っても血が止まらない場合には再度医療機関を受診してください。
関連記事:膝に水が溜まるとはどういう状態?原因や症状について解説
膝の水を抜く前に試しておきたいストレッチ
膝に水が溜まったような症状を感じるものの、すぐに医療機関の診察を受けられないときもあるでしょう。
そのような場合に、ストレッチをお試しいただくことで症状が緩和される可能性があります。
お尻のストレッチ
- 床に座り、左右の足を前方に伸ばす
- 両手をやや後方につき、左右の足を90度程度に曲げる
- 右足首を左膝の上に乗せる
- 上半身をゆっくり起こし、10秒程度姿勢をキープする
- 左右の足を替えて同じ動きをする
上記のストレッチのポイントは、上半身をゆっくり起こしたときにお尻の筋肉が引っ張られるような感覚を意識することです。
前もものストレッチ
- 右方向に体を倒し横になる
- 右腕を立てるようにして上半身を支える
- 左膝を曲げ、左手で左足首を掴む
- 左手で掴んだ足首をゆっくり後方に引っ張り、10秒程度姿勢をキープする
- 左右を替えて同じ動きをする
4の足首を後方に引っ張った際に、太ももの前部分の筋肉が引っ張られるような感覚を覚えるはずです。心地よいと感じる範囲内で、無理をせずストレッチを行ってください。
もも裏のストレッチ
- ベッドに座る
- 右足は床に下ろし、左足はベッドの上に伸ばした状態で置く
- 上半身をゆっくりと左足の方に倒し、10秒程度姿勢をキープする
- 左右の足を替えて同じ動きをする
ベッドの上に伸ばす足は、つま先と膝が上方向を向くようにします。
上半身をゆっくり倒していくと、太ももの内側の筋肉が引っ張られるような感覚を覚えます。
日常生活でできる膝に水が溜まるのを予防する方法
日々の生活習慣や行動を見直すことも膝に水が溜まる症状の改善・予防につながります。
筋トレ・ストレッチ
筋力トレーニングやストレッチは、膝に水が溜まるのを予防するために効果的な方法です。
上記でご紹介した通り、お尻や太ももの筋肉は膝関節を安定的に支える役割を担っていることから、これらの筋力をアップすることで膝に無理な負担がかかりにくくなります。
また、ストレッチを行うことで関節周辺の柔軟性も高まり、腱や軟骨の損傷も予防できます。
ウォーキング
適度なウォーキングは膝関節のスムーズな動きと血行を改善する効果があるため、膝に水が溜まるのを予防する効果があります。
膝関節に過度な負担がかかると症状を悪化させる危険もあるため、痛みや腫れが出るほど長時間歩き続けることは控え、正しい姿勢も意識しましょう。
サポーター・テーピング
膝関節のぐらつきや不安定感を感じる場合には、サポーターやテーピングを使用することで関節が安定し、負担を軽減することができます。
特に運動時などに使用することで、膝への過剰な負荷を防ぎ、炎症を予防できるでしょう。
サポーターやテーピングにはさまざまな製品があるほか、固定の仕方によっても効果は変わってくるため、医師や理学療法士の指導のもと正しい固定方法を取り入れましょう。
アイシング・湿布
外傷や怪我などによって膝関節に炎症・痛みが現れた場合には、早めにアイシングや湿布を行うことが効果的です。
炎症を放置しておくと関節液が過剰に分泌され、膝に水が溜まりやすくなるためです。
アイシングはコールドスプレーではなく、タオルに包んだ”氷のう”や保冷剤などを使用するのがおすすめです。
関連記事:膝の再生医療にかかる費用や名医の探し方|保険適用はされる?
膝に水が溜まってしまった時はイノルト整形外科までご相談ください
膝に水が溜まる原因や疾患はさまざまで、それぞれに合わせた治療法を行わなくてはなりません。
「膝関節に圧迫感がある」、「曲げ伸ばしがしにくい」といった症状を感じた場合には、できるだけ早めにイノルト整形外科へご相談ください。
膝の水を抜く「関節穿刺」はもちろんのこと、保存療法や運動療法、再生医療、手術療法まで幅広い治療法に対応しています。
特に再生医療や体外衝撃波治療、ハイドロリリースなどの最新の医療が対応できる医療機関も限られており、治らなくても様子をみるように言われる整形外科も少なくありません。
詳しい検査を受けたうえで、様々な治療の選択肢から自分にとって最適な治療法を専門医と相談しながら選択できるのがイノルト整形外科の大きな強みです。
もちろん、保険適用を前提とした治療にも対応しているため、まずはお気軽に受診ください。
まとめ
「膝に水が溜まる」という症状はよく耳にしますが、具体的にどういった感覚・症状が現れるのか分からず、放置している患者様も少なくありません。
しかし、治療が遅れると膝関節の状態がどんどん悪化していき、日常生活が困難になるほど重症化するおそれもあります。
今回ご紹介した内容を参考に、膝に水が溜まっているかもしれないと感じた方は、まずは早めにイノルト整形外科へご相談ください。
この記事の監修医師
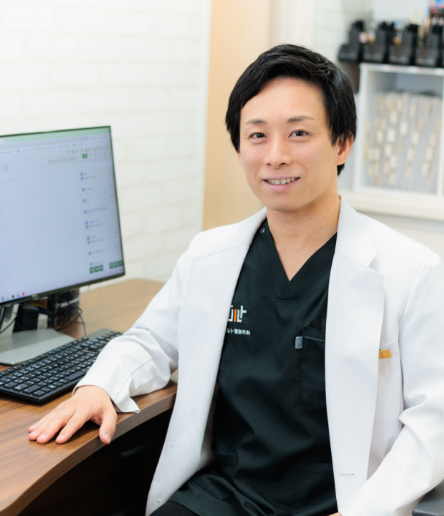
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
渡邉 順哉
経歴
- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒
- 平成23年 東邦大学 医学部卒
- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修
- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科
- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長
- 平成30年 渡辺整形外科 副院長
- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長
- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長