理学療法士 野球動作のバイオメカニズムについての勉強会
※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。
野球は、日本で最も人気のあるスポーツのひとつです。
野球の動作には投・打・走・守・輔などがみられますが、このうち投球動作は野球を構成する最も重要な動作です。
野球の投球動作には、守備位置別にみると異なる運動課題(目的)が要求されます。
すなわち、投手には打者をアウトにするためにストライクゾーンに直球や変化球を正確にかつ速く投げることが、捕手、内野手および外野手には打者走者をアウトにするために他の野手に、すばやい動作でボールを正確にかつ速く投げることが要求されます。
このように野球の投球動作は、状況に応じた複数の課題が組み合わされていることがわかります。
投球障害肩・肘は,投球過多による軟部組織の過度な緊張や疲労を要因とし、その状態でも繰り返し投げ続けることにより発症する身近な問題です。
投球動作のバイオメカニクスでは、投球障害リスクの最小化および投球パフォーマンスの最大化を定量的にめざす。
投球障害に至った投手はそうとはならなかった投手よりも、投球動作中の関節にかかる大きなトルクが加わわり、関節に加わる力やトルクの大きさを関節への負担(障害リスク)の大きさととらえる。
そのため、投球動作中の関節に加わる力とトルクをできる限り低減させ、球速やコントロール、あるいはその両者を維持する/向上させる投球動作を探索することが、投球動作のバイオメカニクスの道筋として重要です。
投球障害肩肘と関連づけられている投球動作中の力とトルクの多くは、「コッキング相から加速・減速相」に当てはまる。
(特にコッキング相後半と減速相からフォロースルー相前半には,肩関節と肘関節に大きな多様な負担が加わる)
リハビリでは、オーバーヘッドスポーツ(野球やバレーボールなど)における下肢・体幹・肩甲胸郭関節での運動連鎖では下肢の柔軟性低下・体幹の可動性低下が生じると肩甲胸郭関節(肩甲骨)などで過剰な代償が生じる可能性があるのです。
再発防止のためにはこれらの機能改善も必要と考えているためエクササイズで柔軟性の獲得は必須事項となります。
この記事の監修医師
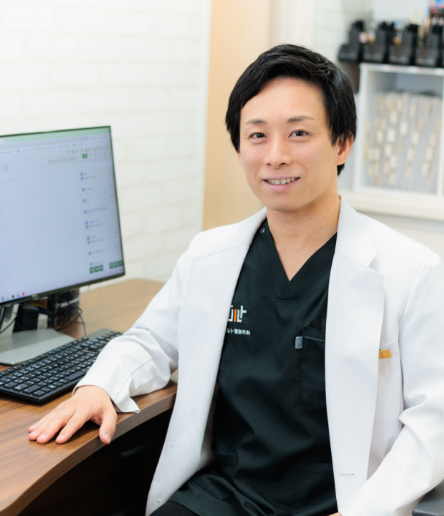
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
渡邉 順哉
経歴
- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒
- 平成23年 東邦大学 医学部卒
- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修
- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科
- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長
- 平成30年 渡辺整形外科 副院長
- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長
- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長