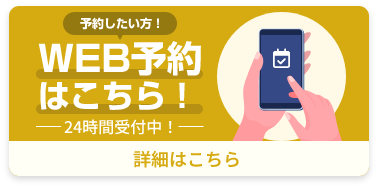橈骨遠位端骨折のアプローチについて
※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。
橈骨は橈骨幹端から骨端にかけて骨皮質に急激な非薄化する。そこで生じる骨折のことを橈骨遠位端骨折。
ではなぜか骨折するか、サルコペニアや転倒しやすいからだ、栄養失調など。
筋力機能低下に伴う環境背景が結果的に転倒しやすい体へ変化していくのです。
骨折の種類として、コーレス骨折(背側転位)とスミス骨折(掌側転位)があり、手もついての骨折が多いため【コーレス骨折】が多い。
術後は軟部組織の滑走が低下(癒着するため)、そのためどこで癒着しているか評価しないといけない。
例えば、手関節を背屈したときに制限がかかるが「手関節掌屈し手指MPjtが可動域上がる場合」は掌側側の軟部組織の癒着と考える。
また手関節掌屈した際のMPjtの制限あるが「背屈位でMPjtの可動域upの場合」は背側の前腕から近位部から手関節部の癒着と考える。
手術による影響として「浮腫も考えられる」
手術侵襲による皮膚損傷により硬化しその近くの静脈も影響を受ける。
そのため心臓に帰る血液循環が悪化し浮腫になる。
また骨折や外傷による深層組織損傷の場合微細動脈が圧迫影響を受け弾性力低下し「動脈内圧が上昇し循環器系に影響を及ぼし浮腫になりやすい。
そのため、皮下組織の柔軟性獲得による静脈還流量の増大や疼痛に伴う血管収縮の抑制を改善しないといけない。
リハビリでは手指や手関節に制限をかけないように、持続強制プラスホットパックや温冷交代浴(温浴:4-5min冷浴:1min ※自律神経過反射を促さないように温浴で終わる)で循環改善することが求められる。
この記事の監修医師
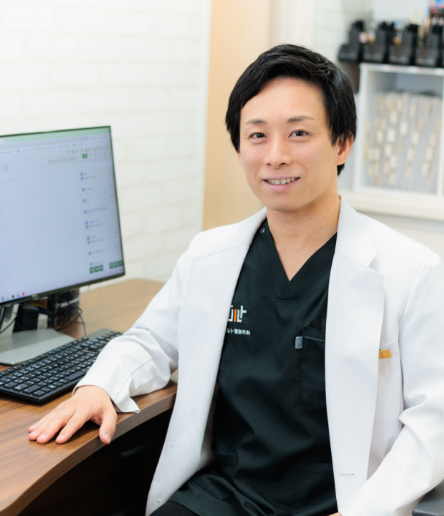
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
渡邉 順哉
経歴
- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒
- 平成23年 東邦大学 医学部卒
- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修
- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科
- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長
- 平成30年 渡辺整形外科 副院長
- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長
- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長