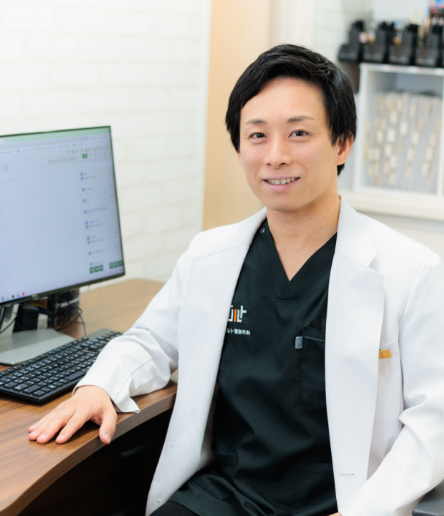リハビリ
理学療法士 勉強会 肩関節
※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。
今回は、結髪動作についてお話しします。
肩関節周囲炎で、結髪動作に制限が起こるケースは多いかと思います。
結髪動作(肩関節外転・外旋)を行う上で、大結節の位置や肩甲骨の動き、胸鎖関節・肩鎖関節の動きなどが非常に重要になります。
結髪動作時、大結節は烏口肩峰アーチの後下方に位置し、接触しやすくなる為、骨頭軸を前下方に位置させるような治療を行っていく必要があります。この時、前提として肩甲骨・肩鎖関節・胸鎖関節の運動がしっかりできている事も重要になります。
肩関節外転・外旋時、肩甲骨は上方回旋・内転・後傾し、鎖骨は胸骨に対いて挙上・後退・後方回旋します。また、その際に肩鎖関節が胸鎖関節に対し挙上位になる必要があります。
次に筋肉に着目して見ていくと、肩関節外転・外旋時にインナーマッスルである棘上筋と棘下筋は短縮方向に移動します。肩関節周囲炎の場合は多くのケースで筋肉が拘縮し、その状態で組織間の粘性抵抗が高くなっています。
本来であれば外転・外旋時、棘上筋と棘下筋は緩みスライドしていくが、癒着が起っているとうまくスライドできず、圧が高まり疼痛が出現します。
その点を考えると、肩関節内転・内旋の可動域も作っていく必要があることがわかると思います。
肩関節内転・内旋に制限があると棘上筋と棘下筋の癒着が考えられます。棘上筋と棘下筋に癒着があると、肩関節外転・外旋時にスライドできず疼痛が出現します。なので肩関節内転・内旋の可動域を作る必要があります。
また、肩関節外転・外旋の制限になる筋肉として、肩甲下筋・烏口腕筋・大胸筋・小胸筋・鎖骨下筋などがあります。このような筋の柔軟性や滑走性を十分に確保することで結帯動作(肩関節外転・外旋)制限の改善につながります。
この記事の監修医師
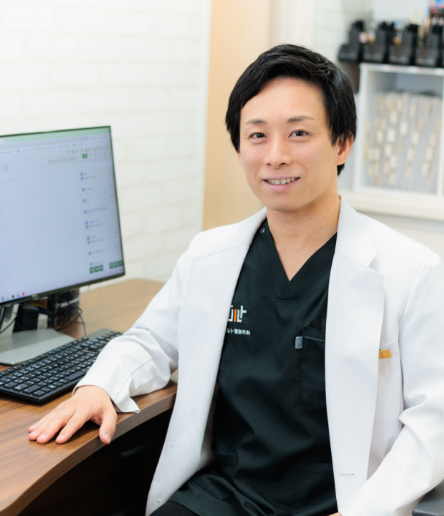
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
渡邉 順哉
経歴
- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒
- 平成23年 東邦大学 医学部卒
- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修
- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科
- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長
- 平成30年 渡辺整形外科 副院長
- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長
- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長