バランス機能について
※本記事は、整形外科専門医・イノルト整形外科 統括院長 渡邉順哉医師の監修のもと執筆しています。
こんにちは! 藤沢の駅前 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニックです。
いつも記事をご覧頂き、誠にありがとうございます。
今回はバランス機能障害について紹介します。
バランス感覚が良いとか、悪いとか一度は聞いたことがあったり、もしくは他人から言われたことがある方もいらっしゃるかと思います。
ではそのバランスはどのように調整しているのか、バランスが悪いとどのようなことが生じるのかを整形外科の観点も交えながら紹介します。
バランスとは姿勢保持や動作時の安定性、不安定性を示しており、協調性や平衡機能にかかわる神経機能を中心にとして以下などを含む複合的な身体機能 (能力)であると言われています。
- 知覚
- 認知
- 骨
- 関節
整形外科疾患や骨変化や筋力低下等の姿勢の変化に起因するものや疼痛や筋出力低下に起因するもの、加齢による視力や固有感覚の知覚低下に起因するものなど紹介していきます。
①姿勢の変化によるバランス機能の低下
整形外科疾患や加齢に伴う脊柱の後弯、骨盤が後傾することで後方重心になってしまいます。
後方重心になることで前後のバランス機能が低下し、特に後方に転倒する可能性が高くなります。
また膝関節が伸びきらなかったり、手術や骨変形による脚長差がある場合は側方へのバランス機能が低下し側方への転倒リスクが高くなります。
②支持性の低下によるバランス機能の低下
抗重力伸展筋(脊柱起立筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋、ヒラメ筋、前脛骨筋)の筋力低下や脊柱や股関節が伸びきらなかったり(伸展制限)、足関節の可動域制限などが生じている場合があります。
また整形外科疾患の変形性膝関節症による大腿四頭筋の筋力低下に伴う疼痛によって支持性が低下している場合はバランス機能が低下しやすいと言えます。
③知覚の低下によるバランス機能低下
加齢による視覚や固有感覚の低下は段差や障害物の認識を遅れやバランス反応が遅れなどにより、段差の踏み外しなどによる転倒につながります。
バランストレーニングのポイント
バランス機能を高めるには脳の情報処理能力の向上やバランス機能を支える感覚器系(視覚や前庭系)や整形外科では欠かせない、筋力や関節可動域など全ての機能の向上が必要になります。
バランス機能の向上を図るトレーニングとして反復学習を行うことで運動学習を行います。 そのため難易度の調整が必要になります。
難易度も簡単過ぎず、難しすぎずが要求されるため、セラピストなどの整形外科でのセラピストの介入が必要になってきます。
藤沢のイノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック スタッフ K&N
この記事の監修医師
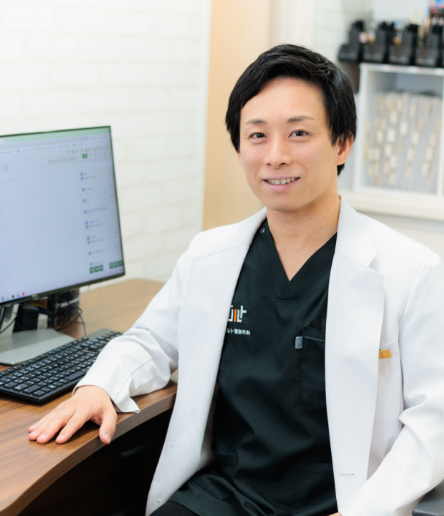
イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 院長
渡邉 順哉
経歴
- 平成16年 鎌倉学園高等学校卒
- 平成23年 東邦大学 医学部卒
- 平成23年 横浜医療センター 初期臨床研修
- 平成25年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
- 平成26年 神奈川県立汐見台病院 整形外科
- 平成28年 平成横浜病院 整形外科医長
- 平成30年 渡辺整形外科 副院長
- 令和元年 藤沢駅前順リハビリ整形外科 院長
- 令和6年 イノルト整形外科 痛みと骨粗鬆症クリニック 統括院長